水色のケーキ 3. [水色のケーキ]
学校祭の第一日目。
ものすごい風が強かったけれど、ものすごい良い天気だった。
学校祭は三日あって、一日に四本ずつの演劇が上演される。一日目は一年から四年まで低学年の発表がある。そうやって学年順に四本ずつグループ分けされているけど、その日の上演順はくじ引きで決められる。
一つの劇は一時間以内の長さということになっている。だいたい皆みっちり時間を使う。ときどきオーバーする学年もいる。短いというクラスは今まで見たことがない。劇と劇との間には二十分の休憩が入る。一つの劇をちゃんと見終わってから、次の学年が用意することができるように取ってある時間だ。その日上演がある学年の人は、もう朝から衣装を着ていることが多いけれど、それでも休憩時間に用意できなくてオーバーする学年がいる。だから絶対に時間オーバーになる。
朝、九時から始まって、午前に二クラスの上映がある。終わる時間に合わせて、十二時前でもランチタイムになって、それが一時間。午後も二クラス。早い時は四時ころに終わり、遅いと七時近くになることもあった。
皆、座ったままだし、つまらないと眠くなってしまうし、腰は痛くなるし、かなり重労働で、その中で自分たちも出るのだから皆、疲れ切ってしまう。
でも、おもしろいものがだんぜん多い。おもしろいとぜんぜん疲れていることに気がつかないし(でも帰ったらがっくりくるけど)、次が楽しみになる。それに一日目は低学年だから、かわいい、楽しいものが多くて、あたしはいつも引き込まれる。今年は一日目の一回目が一年生だった。
あたしはこの学校でもう七回も劇をやったんだな、と思うと心が熱くなってきた。そしてこれが最後の通学校祭になるんだ。そう思うと目がうるうるとしてくるのだった。
あたしたちは八年生だから二日目だ。一日目が終わると、だんだんドキドキしてきて、夜もよく眠れなかった。
今年はアツミさんがくじ引きをして四番目の上演になった。自分の番が終わらないと、ほかの学年のお芝居を見ていてもなんだか気がそぞろで、しっくり頭に入ってこない。自分たちのことばかりが気になって、気持ちがどうも落ち着かなかった。
休み時間の二十分はみなバタバタしている。みんな自分の衣装はもう着ているけれど、楽しみを隠すみたいに、上にコートを着たり大きいスカーフかぶっている。それでもやっぱり休憩時間に用意できない学年もいて、だんだん時間が押されてしまっていた。
三時少し前にやっとあたしたちの番が回って来た。
あたしたちの衣装はすごく簡単。みんなが顔だけ出して、他は黒の洋服。Tシャツでもなんでもいい。黒い布を巻いている人もいる。首にも黒いスカーフを巻いている。顔だけが目立つよう工夫した。
予定通りに真っ暗な舞台。ペンライトでは小さすぎるということになって、けっこう大きめの懐中電灯を一人一つずつ持っている。
ミョウジのシンセサイザーによる『アクエリアス』の演奏に合わせて、あたしたちは一列に舞台に上がった。そして、光が上下に動くように揺らしながら、みんなで舞台をぐるりと一周した。
タタヒロとアツシは結局、二人ともトライアングルを鳴らすことになった。
それぞれがそれぞれの持ち場に立ったり、座ったりすると、一度音楽が消えて静かになる。そして舞台の上手に立ったタタヒロが自分のヘルメットに付いたライトを点けて、トライアングルを鳴らす。
「聞こえる」
アツミさんが自分のライトを点けて言う。
「星のまたたき」
トモミが自分のライトを点けて言う。
タタヒロが自分のライトを消し、舞台の下手にいるアツシがライトを点けて、トライアングルを鳴らす。
また同じように、アツミさんとトモミのセリフが繰り返される。そうやって、劇は始まった。
もっとドキドキするかと思っていたけれど、いざ始まってみるとあたしはちっともドキドキしていなくて、みんなの一つずつのセリフが心の底にまで届いてくるように感じていた。
あたしが最初に考えたシナリオとは、セリフはかなり変わっていた。
たとえば、オハラ レナは自分の好きなもの、やりたいことをセリフにして、星の名前や、どのように舞台を作るのかも自分で考えた。
「ここは花の星、フローラー。ここにはたくさんの花がさいているの」
とレナが言う。
何人かは舞台の背景になって、たくさんの花をかかえてレナの後ろにならぶ。
「季節ごとに、いろいろな色の花が咲くわ。花が咲いていないときはないの。いつでも咲いているの」
うしろの花たちは、音楽に合わせて、揺れている。
「花はみなさんの所に届けます」
花を抱えていたみんなは、前に出て、それを舞台から客席に投げる。
「花を絶やさないように、土を耕して、水がなくならないように、いつでも目を見張って、花が枯れないように、花が一番美しい形で咲けるようにしているのです」
実際、レナは花の種類をよく知っているし、お家でも季節ごとに花を育てるのが好きなのだ。
タカハタ トムのように、自分のこれまでのことをセリフに入れたいという人もいた。
「この星、セルネットは生まれたとき、とてもとても小さかった」
と、トムがささやくように言う。
「そのままにしておいたら、消えてしまう、ゴミのようなものだった」
周りのみんながトムを抱えて、上にあげる。
「たくさんの手がこの星を助けた。たくさんの栄養が必要だった」
トムはみんなにかつぎあげられて、ぐるぐると回る。
「そして、今、やっと一つの星として明かりをともすことができるようになった。この星は少しでも今より明るくなるように、ぐるぐる回っている」
みんなの手を離れてトムは一人でぐるぐる回る。
あたしは、自分の実際のことを自分のセリフで言うなんてことは、できない。あたしの生活のことなんか、何一つ人に伝えたいなんて思ったことはなかった。だから、まったく空想だけのセリフだった。
「みなさん、見えますか」
と、あたしはライトを振る。
「今、この星は生まれました。できたてのホヤホヤです。名前もありません」
あたしはあたしの身に着けている黒い布の中から、白い布を出して、広げる。
「ここは新しい宇宙の中継ステーションになります。いろいろな星がここを拠点にして、連絡を取り合うのです。放送局のようなものですね。たくさんの音楽も発信されています!」
音楽係のタタヒロとアツシが、ちょっとずつ、いろいろな音楽をつぎはぎした音を流す。
「音はここで生まれ、たくさんの星にとどくのです」
そして、アツミさん
「今日は、星の博覧会にようこそいらっしゃいました」
アツミさんが黒い布を取ると、鮮やかな水色の衣装が出てくる。
「私は、空、そのものです。空だけでは何もないのと同じ。そこに星がまたたいていて、やっと空と呼べるものになります」
アツミさんが手を広げると衣装はパーッと一緒に広がって、ふわふわと揺れる。
まわりのみんなは風船を膨らまし始める。
「空には、たくさんの星のエネルギーが詰まっています。ほら」
膨らませた風船を手放すと、風船が、それぞれに勝手な方向に飛んでく、風船を手放した星たちはまた次の風船を膨らませる。
「それぞれの星にそれぞれの思いがあります。夜空を目を凝らして見てください。星は瞬いています。それは星からあふれた思いです」
あたしが最初に考えていたのとは、かなり違ったものになったけれど、でもそれで良かったと思う。あたしが考えたセリフのままでいいという人はそのまま、あたしのセリフを使ったけど、それでもかなり直したし、実際にそれを言う時には何かしらが変わって行った。その人自身の言葉になるのだ。
みんなで作り始めたら、どんどん違う考えも出てきて、周りの人たちの動きをどうするか、背景をどうするか、つぎつぎに意見が出てきてふくらんでいった。
風船を膨らませるというのは、アツミさんの考えだったし、音楽担当は皆の希望に合うように音楽を探し、考え、それがダメだと言われればまた探し、考えた。全員が参加して、セリフを言いたくなくても、ただ舞台に立って、ライトを点ける。それでりっぱなその人の役になるのだ。
あたしは、かなり満足して、宇宙を舞台にするのは、すごくいい考えだったな、と自分でちょぴり自慢したい気分になっていた。
やっと自分たちの演劇が終わったことで、あたしはすごくホッとしていた。最後だと思うといろいろな思いが押し寄せてきていて、頭にその思いがいっぱいになっていて、言葉にするには難しい感じだった。
三日目。最後の劇が終わった後、校長先生のお話があり、十二年生とのお別れのあいさつが終わった。会場からどどっと人が帰って行って、会場にはどんどん人がいなくなる。片付けの生徒がお掃除を始めて、あたしもそれを手伝った。
トモミもイスなどを片付けていて、ときどき目が合うと、笑いあった。アツミさんも片付けていたけれど、アツミさんはまた以前の固い表情になっていて、誰とも目を合わせないでもくもくと片付けていた。
アツミさんは、帰りがけにあたしの所にやってくると、
「成功だったね! ありがとう。あたし、なんだか頭が痛いから、もう帰るね」
と例のとろけるような笑顔で言った。頭が痛いのに…。あたしはそのアツミさんの後姿をしばし見つめてしまった。
アツミさんは出口近くにいたトモミにも声をかけて、トモミも何か言って、そして会場を出て行った。
あたしはなんだか一人で帰りたくない気分だった。そのあたしの気分が通じたかのように、トモミがまたいつものように走り寄ってきた。でも、何か少しおかしい。トモミはなんだか少しさびしそうに笑うと
「ね、今日、どこかに寄って帰ろう!」
と言った。
「うん。あたしもそんな気分だったの。寄って帰ろう!」
あたしも心の底からそう思っていた。
「ねえ、少し静かな場所がいいな。ヒトミに話しておきたいことがあるから」
トモミがやけに真面目に言う。
「話って…。いつも話して帰っているじゃない。毎日のように!」
「そうだけど…。座って、ヒトミの目を見て、まっすぐ話したい」
「げ! なに、それ。重たい話ってこと?」
「そういうわけじゃないけど。アツミさんのこと、話したい」
あたしはちょっとムッとした。昨日だって一緒に帰ったのだから、昨日言っておいてくれたのなら良かったのに。
「パーラーに行きたいな」
「うんいいよ」
あたしも、まだ引っ越しすること、ママと一緒に暮らすことをトモミに話していなかったじゃないか。それを話すちょうどいい機会かもしれないと思った。
あたしは、トモミをスクーターの後ろに乗せて、少し遠くのミキムラのフルーツパーラーに行くことにした。本当は二人乗りは得意じゃないけど、しょうがない。念のためにいつも予備のヘルメットをサドルの下にしまってある。
ミキムラのフルーツパーラーには、ママと一緒に行ったことがある。でもお友達と一緒に行くのは初めてのことだった。
お店の前に小さい花壇があって、その花壇の見える席があたしのお気に入りだ。
そのお気に入りの席が空いていたので、二人で喜んだ。
「ミキムラ、あたしも大好きだよ! いつもママと来るの!」
とトモミが言った。
メニューを見て、すごく二人で悩む。絵本みたいに、色鉛筆描きのパフェがたくさんならんでいる。そのページを見ているだけで楽しい。
「あたしは、やっぱりイチゴだな」
とトモミが先に決めた。
「うーん。悩むけど…、あたしもイチゴかな」
ふたりで同じイチゴパフェをたのんで、むかい合うと、なんだかすごく変な感じがした。トモミと仲良くなってからこの二年、いつも教室の隣の席か、スクーターを押しながら並んで帰る時におしゃべりしていたけれど、こんな風にかしこまって向かい合って座ったことがなかったのだ。
「ねえねえ、話って何?」
「すごいこと」
トモミが目を輝かせる。
「あのね。アツミさんが、先週、うちに遊びに来たの」
あたしは、たぶん、目をパチクリした。
「ね。ごめん。ヒトミ。なんでヒトミのことお家に誘わなかったのかって、ヒトミ、そう思うよね。まず、そのことから話さなくちゃあならない。だから、ちゃんと座ってお話したかったの」
あたしは、たぶん、まばたきもできなかった。いったい、なんと返事したらいいのか、見当もつかなかったのだ。
「ね、あたしのママのこと話したことあるよね」
「う、うん…、なんのことだっけ?」
「ママってね、すごく身体が弱いってこと」
「そういえば…、そうだったかな?」
「ママはね、とにかくあたしのことをすごく心配してくれるの。あたしのこと、宝物って言ってくれる。そしてね、あまり心配しすぎると、寝込んじゃうの。それはね、時としてすごくわざとらしいな、と感じることもある。あたしが、だんだん大人になってきて、そういうことがね、見えるようになってきたの」
「うん」
「ママはね、桜東通学校に通うことには、反対だったんだよ」
そこで、二つのパフェが運ばれてきて、ウェイトレスさんがいなくなるまで、話はちょっとお休みになった。
二人の間にパフェが並ぶと、顔が少し隠れるし、パフェに少し気持ちが動くから、話が聞きやすくなったように感じた。
「もともとママはあたしのこと、外に出したくなかったの。どうしてお家でサテライト校を受けないのかって、毎日のように泣いて、泣いて、トモミはママよりも学校のお友達と仲良くなって、それで幸せなの? なんて言うんだよ。まいっちゃうよ。それに、どうせ通学校に通うのなら、もっとお金持ちの人が集まっている良い学校、セキュリティーがしっかりしている通学校にしなさい、って言ったの」
あたしは、だんだん返事をするのが面倒くさくなって、イチゴを突っつきながら、目で相槌を打って、聞いていた。
「あたしは、ママとはうまくやって行きたいって思ってる。ママを怒らせたくないし、泣かせたくもない。ママとお買い物に行くのは楽しいし、お話するのも楽しい。ママがいつも気持ち良く、あたしのことかわいがってくれる時が好き。
でもさ、どうしても桜東通学校に行きたかったの。だって、あたしが知っている昔の学校の様子に一番似ているし…、ママやママのお友達のおばさま方のことも好きだけれど、ママやおばさまたちが、好きなものは、あたしが本当に好きなものとは違う。あたしは本を読んだり勉強したりすることが好きで、桜東通学校ではそれがすごくシンプルな形でできそうな気がしていたの。それに皆で演劇をするのもおもしろそうだった。
キヤ シンヤってうちの通学校の出身だよね? 俳優ではダントツうまいって思わない? そういうところではけっこう評価されてるもん。うちの学校。
でもママにはそんなこと言ったってわからないだろうし、あたしが説明してわかってもらう気もなかった。だから、ママの言うとおりの通学校に通おうかなとも思っていたの。」
「… …」
「でもね、でもね、パパが言ってくれたの『学校くらい、トモミの好きな所に通わせてあげよう』って。『自分の行きたくない学校にいやいや通うなんて、させたくない』って。それってすごかった。いつもパパはママを大事にしていて、ほとんど何も言わないから、それがすごくカッコよくて、重たくて、ママもはは~って、何も言わなくなった。あたしはうれしかったよ」
「…、…」
いったいトモミはこんなに遠くの方から話をして、何が言いたいっていうんだろう。あたしにはまだ見当もつかなかった。
「でもね。あたしが桜東通学校に通うことが決まってからは、ママは寝込むことが多くなった。お家に帰ってもね、具合が悪いって言って寝ているの。お食事とかはちゃんと家政婦さんが来て作ってくれていたし、あたしは、ママに顔を見せて、ママのお話を聞いて、お家にいる時はママが喜ぶようにしていたの。
一年経った頃くらいから、ママも慣れてきて、あたしの通学校のお話を聞きたがったり、あたしのお友達に会いたいと言うようになってきたの。そのころから、ママは学校のお友達を連れていらっしゃって言ってくれるようになったの。あたしもお友達にお家に来てほしいとずっと思っていた。いつも。一番、ヒトミに来て欲しいと思っていた。いつも」
声に出さなかったけれど、「あ!」と心の中で思った。いつもトモミが言いたそうで言わない言葉。「ねえ、ヒトミこんどさ…」。で、あたしが聞き返すと「なんでもない」って言う。あの言葉に続くのは「お家に遊びに来て」っていうことだったのだ!
「でも、あたしにはわかっているの。ママはヒトミのことが気に入らない」
びっくりした。こんなこと、真正面から言われるなんて。
「ママは、いつも言っている。ヒトミが住んでいる地区の人とは付き合ってはいけませんって。桜通学校にはそういう所からも子供が通ってきているから、だから反対したのだって。そういうお友だちには気をつけなさいって。
もちろん、あたしはちゃんと説明して、ママにわかってもらおうとも思った。でもわかるんだよ。ママの心の中にはすごい厚い壁みたいなものがあって、それは今のあたしの力ではどうやっても動かせないものなの。それを動かそうとすると、ママも具合が悪くなるし、あたしもすごく暗い気持ちになる。
その点、アツミさんだったら、大丈夫。アツミさんの住んでいる所は問題ないし…。それにアツミさんはステキだから、お話ししてみたいと思っていたから、思い切ってあたしが誘ったら、すぐに来てくれたの。
ヒトミのおかげだよ。あの劇の練習が始まってから、あたし、すごくアツミさんと話しやすくなったの。セリフをどういう風に言ったらいいかとかね、お話しするきっかけがたくさんできたの。でね、アツミさんって一度話してみるとね、とっても暖かくて、良くて、楽しい人なんだよ! ヒトミのこともほめていたよ。あのシナリオがあったから、どんどん話が進んで、みんなでまとまって良かったって」
あたしは何でもないような顔をして、パフェをもう半分食べていた。今までに感じたことのないようなヘンテコな気分だった。
「怒った?」
あたしがずっと黙っているからか、トモミが気にして、聞いてきた。
「怒ってない」
「じゃあ、何か言って。今までのところまでの話、どう思う?」
「どうって…」
あたしはパフェをかき回す。
「トモミのママが言っているのはおじいちゃんのことだよね。たぶん、おじいちゃんが『外された』人だからだよね。」
「そこまで…、わからない」
「そうだよ。でも、おじいちゃんは犯罪者じゃないよ。ただ、おじいちゃんが正しいと思ったことを通そうとしただけなんだよ。それがおじいちゃんの勤めていた会社の偉くて裕福で、代々そうやって偉くて裕福に暮らしている人のことを脅かしたの。おじいちゃんは会社を辞めさせられたし、いい仕事にも就けなくなってお、お金もなくなった。
でも、おじいちゃんは、今だってその考えを間違えているとは思っていないよ。ただ、今の世の中には通用しない。長いこと押さえつけられて、エネルギーもなくなった。だから、静かに暮らしているんだよ。おじいちゃんがどんなにやさしくて、ステキで、あたしのこと思って、毎日真面目にしっかり働いているのか、あたしは毎日見ているから、よく知っている」
おじいちゃんのやさしい笑顔が浮かんで、あたしの目から涙がこぼれた。
「ごめん。ヒトミ」
「いいの。これは説明とかしてわかることじゃないから…」
「それで、こう言いたいの。あたしは、ママのお家でママの世話になっているうちはヒトミをお家に誘うことはできない。ママによけいな心配かけたくないし。桜東通学校自体のこと、だめな所だと思って欲しくないし、いろいろ言って欲しくないから」
「そんなこと、どうでもいいよ」
「よくない。まだ続きがあるの」
トモミって、なんでこんなにまで正直に、あたしが嫌な気になることまで全部あたしに話してしまうんだろう。あたしは、つい溜息ついてしまって、ぼんやりとトモミを見つめた。
「あたしは、ずっとヒトミとお友だちでいたい。こんな風に、ヒトミを邪魔にしたみたいにしてアツミさんを誘ってしまったけど、そのことについては、気を悪くしたとしてもしょうがないと思ってる。あたしはいつか、ママの手を離れて、あたしの考えだけで生活できるようになったら、いつか、ヒトミ、あたしの家に来て!」
「バカみたい!」
と言って、あたしは笑った。
「いつも、あたしのこと『ぐるぐるの考え』になってるって、トモミはからかうけど、今日はトモミがぐるぐるの考えになっているよ。それに、まだ、そんな先のことまでわからないよ! その時になっていないんだから、今から約束しても意味がないよ」
「でも言って! ずっとお友達でいてくれるって!」
あたしはすっかりシラケ切ってしまって、今流した涙が嘘のように引っこんだ。あきれた顔を隠すように、グラスの底に残っているアイスを長いスプーンでかきあつめた。
「あたしも、トモミに言わなければならないことがあった!」
今度はあたしが話す番だった。
あたしは、ママと東京で暮らす決心をして、もう四月には桜東通学校から転校することをトモミに言った。
「ウソ!」
トモミは、悲しそうに言った。
「ホントだよ。いつだって」
「あたしが、アツミさんと仲良くなったからって、それだからって、意地になっているんじゃないよね?」
「バカじゃないの? それを知ったのは今日でしょ! 違うに決まっているじゃない」
「じゃあ、遠く離れても、友達でいよう!」
「トモミ。わからないよ。友だちでいようなんて…それは、自然に続いたり、続かなかったりすることで、約束したりすることじゃないと思う」
きっぱり言うとトモミの顔がなんだかごっつくなったので、すかさず付け加えた。
「でも、あたしは…、トモミと友達でいたいって思っているよ」
「ありがと!」
ごっつい顔がほころんだ。
「今のところはね!」
そんな先の約束まで自信が持てないから、ついそう言った。こういう時には、どうでもいいって気持ちになってしまう。
「ヒトミって、なんか冷めてる」
「トモミって、なんか暑苦しい」
いつもだったら、ここで二人で大笑いしていたのかな? でも今はそういう気にはなれなくて、ちょっとニッコリして、あたしはトモミをトモミのお家の近くまでスクーターで送って行った。
スクーターから降りたトモミが、急に泣き出した。しゃくり上げるように泣いて、泣いて、止まりそうもなかった。「バイバイ」も言えなくて、ちょっと手を上げると、泣きながら家に向かって行った。
「この、スクーターの名前はラビットだよ!」
トモミの背中に向かって、あたしが言った。ほかに言う言葉を思いつかなかった。
「うん。わかってる」
トモミは振り返って涙を拭うと、悲しそうに笑って、お家の方に走って行ってしまった。
それから、八年生の最後の日まではたった三日しかなかった。
最後の日に、あたしとトモミはとうとうアツミさんに水色のケーキをプレゼントした。
「一緒に食べませんか?」
とあたしが声をかけて、ホールで三人で座った。
ケイエスのケーキの箱の中には、三つの水色クリームのケーキが入っていた。
「ああ、これ。ブルーベリーよね」
アツミさんが言った。
なんだ、やっぱり知っていたのか、知らないのはあたしだけだったのか。
「ここのケーキはどれもおいしいよね」
アツミさんが喜んでくれたので、あたしはうれしかった。
「残念ね、ヒトミさんが学校を辞めてしまうなんて」
「ええ。でも、来年の通学校祭には見に来たいなと思っているから、みんなにがんばってもらいたいな」
「そうね」
「ねえねえ、なんでヒトミがアツミさんにそのケーキプレゼントしたいか、知ってる?」
トモミが話に入り込んできた。
「アツミさんがいつも水色のお洋服を着ているから、水色のクリームのケーキだって! お洋服の色と食べ物なんて、関係ないのに」
フフフとトモミが笑うと、アツミさんがちょっと不服そうな顔をした。
「水色か…」
あたしとトモミがちょっと目くばせする。
「これは、空色って言ってもらいたいな」
アツミさんは自分の着ているシャツを引っ張った。
「水の色って、もっと強い色よね」
「強い?」
あたしとトモミが同時に声を上げる。
「そう。太陽の下で光っている海って、グリーンだったり、マリンブルーっていうみたいにもっと濃い色だったり、『ここにいます!』っていう、強い感じがする。
あたしのイメージする色は空色で、もっと薄くて、何もないかなって感じの色」
「そう?」
「そうよ。この世から消えてなくなってしまいたいな、って思った時に、あ、空になればいいんだ、って思ったの」
「へえ~」
言いながらも、アツミさんのセリフを思い出した。
『空だけでは何もないのと同じ。そこに星がまたたいていて、やっと空と呼べるものになります』
「それに、空には触れない! 水には触れるけど」
あたしとトモミはうんうんとうなずき合った。
ホールを出ると、「じゃあね」と手を振って、アツミさんが先に帰って行った。
あたしとトモミはいつものようにスクーターを引っ張りながら、並んで歩いた。
「落ち着いたら、遊びに来て」
あたしが言った。
珍しく、トモミは何も返事せず、下を向いてしまった。
「大丈夫だよ。今度はおじいちゃんの家じゃないから、遊びに来ても」
そういえば、あたしにはお家にお友達を呼ぶ、なんて発想はなかったんだな。今までは。
「いつかさ、家にも遊びに来て」
トモミが言って、別れた。
もう桜東通学校には来ないんだ。ここに来ないあたしって、どんな生活になるのだろう。あたしはスクーターに乗って、いろいろ新しい生活を想像していた。
四月。新しい生活が始まった。
ママのマンションは高いビルの二十一階だった。家の外は車も人も多くて、「さすが都会」とあたしは思った。
おじいちゃんの暗い湿ったお家に暮らしていた毎日は、どんどん遠のいていった。
あたしは、九年生になり、中央公園通学校に通うことになった。ここもとてもシンプルな通学校だった。家から歩いて通える。中央公園の中にあって、図書館とカフェ、公園事務所が一緒になっている三階建てのビルの三階に教室がある。木々に埋もれているから、森の中の学校みたいに感じる。ちっとも都会って感じがしない。あたしは見学に来て、一度で気に入ってしまった。
九年生は十人。そのうち八人が女子でみんなとはすぐに仲良くなれた。まだ一緒に帰ったり、お家に行ったりというようなお友達はいないけれど、みんなサッパリしていて、自分の世界を持っているっていう感じで、これから、いろいろわかってくることがあるのかな…。とっても楽しみだ。
ママは遅くなることが多いので、家で一人で過ごすことが多いけれど、勉強したり、本を読んだり、時々おじいちゃんやトモミに電話してみたり、好きな映画やアニメを見たり、絵を描いたり、パソコンをやったり、やることはたくさんある。
おしゃれな雑貨屋さんやスイーツの店、お洋服のショップなどがあって、街を歩くのも楽しかった。
それに…、ママが忙しいので、あたしが料理をすることにした。パソコンでいろいろな料理のレシピを探して、近くのスーパーに材料を買いに行く。おじいちゃんが作ってくれた煮物の味を思い出して、おじいちゃんに作り方を聞いたり、モロッコとかポルトガル風なんていう料理を自分なりにアレンジしてみたりして、まだこちらに来てやっとひと月だけれど、毎日すごく「充実してる」という感じがしていた。
五月の連休にはおじいちゃんの家に行ったり、その間にトモミと会ったり、おじいちゃんの畑を手伝うことにしていて、それも楽しみだった。
「ね、ヒトミに会ってもらいたい人がいるの」
連休になる二日前の朝、あたしがお弁当を詰めていると、仕事に出かける前に、ママが急にあたしの後ろからあたしの両肩を両手で軽くつかんで、そう言った。
あたしが振り返ろうとすると、
「こっちを見ないで聞いて」
と言うのだ。あたしは返事できなくて、目をパチクリした。
「あのね。その人はヒトミのパパなの」
あたしはますます返事ができなくなって、こんどは瞬きもできない感じになって、顔が強ばった。
「ヒトミがおじいちゃんの家にお泊りに行く前にね、会ってほしいの。だから…、もう明日しかないから、明日の夜にね、どこかでお食事しよう。心づもりしておいてね。じゃあね、行ってきます」
ママはそれだけ言うと、先にさっさと仕事に出かけてしまった。
あたしは身体も頭の中までも固まったしまったみたいになって、次に何をしていいかわからなくなった。
「そうだ! お弁当、お弁当」
と自分に言い聞かせるように言うと、中身を詰めたお弁当箱をハンカチでくるんで、リュックに入れた。そうしたら、猛烈に腹が立って来た。
なんだって、ママは急に、こんな朝に、大事なことをいとも簡単に言うのだろう。あたしの目も見ずに! すごく複雑な気持ちがぐるぐる渦巻いてきて、涙が流れてきた。ママって勝手すぎる!
そのまま、今手に持っているものを全部ぶん投げて、テーブルも何もひっくり返してしまいたいような気持になった。でも、もう学校に行く時間だった。あたしは顔を洗い直し、深呼吸して、自分の顔を見つめた。
目が赤い。
「ママのバカ! バカ! 大バカ!」
鏡の中のあたしに訴え、タオルをぐるぐると振り回した。それでも腹が立って、バシバシとタオルで流しを鞭打った。深呼吸した。さらにもう一度気持ちを落ち着けて、学校に向かった。
いろいろ、わからないことが頭の中でぐるぐる渦巻いていた。なんだって、今なの? パパの話なんて、一度も聞いたことがないのに! どうしてママはいつも急にそういうこと言うの? いったいどこのだれなのだろう。パパって。
ありがたいことに、学校に行ってしまったら、少しは気持ちが紛れた。ママはそれを計算して、朝のバタバタしている時にあたしに言ったに違いない。一緒に暮らすようになったら、ゆっくり話ができるなんて、うそっぱちだったじゃないか!
結局、ママはいつも忙しくて、あたしが寝てから帰ってきたり、あたしが学校に行く頃には眠っていたり、今日みたいにあたしより早く出て行ってしまったり、こういうの「すれ違い」って言うんじゃなかったっけ? そうして、あたしに考える時間を与えずに、もう「明日」パパと会う約束をしていたんだ! あたしの時間なんか気にせずに。
また腹が立ってきた。
でも、まだトモミみたいな友達はいないから、それを誰かに話すわけにもいかない。
結局、あたしはどうすることもできずに、その日、ママの帰りを待った。
ママとは話せないまま夜になった。その日もママは遅くて、あたしは先に寝ることにした。でも頭の中がぐるぐるしていて、ちっとも眠くならない。
もう明け方になってから、ぐうっと眠った。アラームが起きる時間を告げても、身体が言うことをきかない。どうにかこうにか起き上がって、キッチンに行くと、ママのボイスメールがあって、今日、パパという人と会う時間と場所が入っていた。
ママに話しかけようと思ったけれど、ママはぐっすり眠っていた。しょうがない。覚悟を決めよう。お弁当は作ることができなかったっし、朝からヘトヘトっていう感じだった。やっとこ学校に行った。一日、気もそぞろだった。
一日通学校に通うことがこんなにも重労働みたいになるなんて! 通学校を出るころになっても、まだお腹の中にフツフツとママに対する怒りの塊が残っていた。
中央公園通学校のある公園を出たところに、深緑色のジープが止まっていた。そこが待ち合わせ場所。そのジープの窓からママが手を振った。まったく、いい気なものだ。あたしは知らん顔して通りすぎてやろうか、と思った。
あたしの顔はふくれ面だった。と、運転席に座っていた男の人が出てきて、あたしにあいさつした。ごっついジープだったからごっつい人が出てくるのかと思ったけど、細い、優しそうな目をした人が出てきて、男の人というよりは中性的な感じだった。
そして、「ヒトミ シンタロウと言います」と手を差し出した。
あたしは、心臓が止まるかと思った。「ヒトミって…」。
その人は、ニッコリ笑うと、「さあ、乗って、乗って」と助手席のドアを開けてくれた。
「ねえヒトミ、もしパパと暮らして、パパの名字をもらったら、ヒトミ ヒトミだったね」とママが笑いながら続けた。「今からでももらえるのよ。その名前が良かったらね」
街には不釣り合いなジープは走り出し、涼やかな風が入ってきた。
「今日はテントでできた個室のあるレストランに行こう。そういうのヒトミちゃんは好きかな?」
「おいしいものが出てくれば、なんだって好きよ。ね、ヒトミ?」
ママが勝手にあたしの気持ちを言う。また腹が立ってっきて返事をする気になれない。あたしの頭の中は真っ白だった。でも、このシンタロウって人の話を聞いてもいいかなと思い始めていた。その声はすんなりとあたしの心に届くような感じがした。
「おじいちゃんは、元気かな」
ポツリとあたしが言った。調子のいいママに釘を刺したい気持ちだったのだ。
「元気よ。それに、もうすぐ会えるでしょ」
あたしが黙っていると、ママはまた勝手に話し始めた。
「ヒトミはおじいちゃんのお家の方に住んでいた方が良かったの?」
「べつに…」
「ママはね、どうしてもあのお家を出たかったの。それは、おじいちゃんを否定するという意味じゃないの。あの場所にいるとね、レッテルを貼られてしまうの。それは、ママには耐えられないことだったの。でもね、レッテルははがれない。出たくて出たくてがむしゃらにいろいろなことやって、ママはやっとそれに気が付いたの。貼られても気にならないようになるしかないんだなって。それがやっとできるようになったのよ」
「そう?」
「ママはうれしい。ヒトミはそんなこと気にせず育ってくれて」
「そう?」
「そうだよ。ママもヒトミを見習わなくちゃ」
「ママ、あたしはただおじいちゃんが好きなだけだよ。それに、空になればいいんだよ。空にはレッテルが貼れないから」
あたしはぼんやりとアツミさんと話したことを思い出していた。
ジープの座席は少し高いから、行きかう車を見下ろしているみたいでおもしろかった。
「ね、ヒトミ、こちらのヒトミさんと来月、インドネシアに行くことになったの。お仕事がらみだけどね、ヒトミも行くでしょ?」
ママがまた勝手なことを言っている。
「一緒に行ってくれるとうれしいな」
シンタロウさんがこっそり言った。
返事はしたくなかった。あたしは明日のお弁当のことを考えていた。今朝、持っていけなかったから、その分をお弁当にして、おじいちゃんの分も作って持っていこう。冷蔵庫に残しておいたって、ママは食べやしないから、たくさん作って持っていこう。だって、自分で作れる小さいことしか想像できないし、どうせあたしの思った通りにはいかないのだもの。そのほかのことは、考えたってしょうがない。
今はただ、ジープの外の景色と、これから行くレストランのことを楽しみにしよう。
(おしまい)
ものすごい風が強かったけれど、ものすごい良い天気だった。
学校祭は三日あって、一日に四本ずつの演劇が上演される。一日目は一年から四年まで低学年の発表がある。そうやって学年順に四本ずつグループ分けされているけど、その日の上演順はくじ引きで決められる。
一つの劇は一時間以内の長さということになっている。だいたい皆みっちり時間を使う。ときどきオーバーする学年もいる。短いというクラスは今まで見たことがない。劇と劇との間には二十分の休憩が入る。一つの劇をちゃんと見終わってから、次の学年が用意することができるように取ってある時間だ。その日上演がある学年の人は、もう朝から衣装を着ていることが多いけれど、それでも休憩時間に用意できなくてオーバーする学年がいる。だから絶対に時間オーバーになる。
朝、九時から始まって、午前に二クラスの上映がある。終わる時間に合わせて、十二時前でもランチタイムになって、それが一時間。午後も二クラス。早い時は四時ころに終わり、遅いと七時近くになることもあった。
皆、座ったままだし、つまらないと眠くなってしまうし、腰は痛くなるし、かなり重労働で、その中で自分たちも出るのだから皆、疲れ切ってしまう。
でも、おもしろいものがだんぜん多い。おもしろいとぜんぜん疲れていることに気がつかないし(でも帰ったらがっくりくるけど)、次が楽しみになる。それに一日目は低学年だから、かわいい、楽しいものが多くて、あたしはいつも引き込まれる。今年は一日目の一回目が一年生だった。
あたしはこの学校でもう七回も劇をやったんだな、と思うと心が熱くなってきた。そしてこれが最後の通学校祭になるんだ。そう思うと目がうるうるとしてくるのだった。
あたしたちは八年生だから二日目だ。一日目が終わると、だんだんドキドキしてきて、夜もよく眠れなかった。
今年はアツミさんがくじ引きをして四番目の上演になった。自分の番が終わらないと、ほかの学年のお芝居を見ていてもなんだか気がそぞろで、しっくり頭に入ってこない。自分たちのことばかりが気になって、気持ちがどうも落ち着かなかった。
休み時間の二十分はみなバタバタしている。みんな自分の衣装はもう着ているけれど、楽しみを隠すみたいに、上にコートを着たり大きいスカーフかぶっている。それでもやっぱり休憩時間に用意できない学年もいて、だんだん時間が押されてしまっていた。
三時少し前にやっとあたしたちの番が回って来た。
あたしたちの衣装はすごく簡単。みんなが顔だけ出して、他は黒の洋服。Tシャツでもなんでもいい。黒い布を巻いている人もいる。首にも黒いスカーフを巻いている。顔だけが目立つよう工夫した。
予定通りに真っ暗な舞台。ペンライトでは小さすぎるということになって、けっこう大きめの懐中電灯を一人一つずつ持っている。
ミョウジのシンセサイザーによる『アクエリアス』の演奏に合わせて、あたしたちは一列に舞台に上がった。そして、光が上下に動くように揺らしながら、みんなで舞台をぐるりと一周した。
タタヒロとアツシは結局、二人ともトライアングルを鳴らすことになった。
それぞれがそれぞれの持ち場に立ったり、座ったりすると、一度音楽が消えて静かになる。そして舞台の上手に立ったタタヒロが自分のヘルメットに付いたライトを点けて、トライアングルを鳴らす。
「聞こえる」
アツミさんが自分のライトを点けて言う。
「星のまたたき」
トモミが自分のライトを点けて言う。
タタヒロが自分のライトを消し、舞台の下手にいるアツシがライトを点けて、トライアングルを鳴らす。
また同じように、アツミさんとトモミのセリフが繰り返される。そうやって、劇は始まった。
もっとドキドキするかと思っていたけれど、いざ始まってみるとあたしはちっともドキドキしていなくて、みんなの一つずつのセリフが心の底にまで届いてくるように感じていた。
あたしが最初に考えたシナリオとは、セリフはかなり変わっていた。
たとえば、オハラ レナは自分の好きなもの、やりたいことをセリフにして、星の名前や、どのように舞台を作るのかも自分で考えた。
「ここは花の星、フローラー。ここにはたくさんの花がさいているの」
とレナが言う。
何人かは舞台の背景になって、たくさんの花をかかえてレナの後ろにならぶ。
「季節ごとに、いろいろな色の花が咲くわ。花が咲いていないときはないの。いつでも咲いているの」
うしろの花たちは、音楽に合わせて、揺れている。
「花はみなさんの所に届けます」
花を抱えていたみんなは、前に出て、それを舞台から客席に投げる。
「花を絶やさないように、土を耕して、水がなくならないように、いつでも目を見張って、花が枯れないように、花が一番美しい形で咲けるようにしているのです」
実際、レナは花の種類をよく知っているし、お家でも季節ごとに花を育てるのが好きなのだ。
タカハタ トムのように、自分のこれまでのことをセリフに入れたいという人もいた。
「この星、セルネットは生まれたとき、とてもとても小さかった」
と、トムがささやくように言う。
「そのままにしておいたら、消えてしまう、ゴミのようなものだった」
周りのみんながトムを抱えて、上にあげる。
「たくさんの手がこの星を助けた。たくさんの栄養が必要だった」
トムはみんなにかつぎあげられて、ぐるぐると回る。
「そして、今、やっと一つの星として明かりをともすことができるようになった。この星は少しでも今より明るくなるように、ぐるぐる回っている」
みんなの手を離れてトムは一人でぐるぐる回る。
あたしは、自分の実際のことを自分のセリフで言うなんてことは、できない。あたしの生活のことなんか、何一つ人に伝えたいなんて思ったことはなかった。だから、まったく空想だけのセリフだった。
「みなさん、見えますか」
と、あたしはライトを振る。
「今、この星は生まれました。できたてのホヤホヤです。名前もありません」
あたしはあたしの身に着けている黒い布の中から、白い布を出して、広げる。
「ここは新しい宇宙の中継ステーションになります。いろいろな星がここを拠点にして、連絡を取り合うのです。放送局のようなものですね。たくさんの音楽も発信されています!」
音楽係のタタヒロとアツシが、ちょっとずつ、いろいろな音楽をつぎはぎした音を流す。
「音はここで生まれ、たくさんの星にとどくのです」
そして、アツミさん
「今日は、星の博覧会にようこそいらっしゃいました」
アツミさんが黒い布を取ると、鮮やかな水色の衣装が出てくる。
「私は、空、そのものです。空だけでは何もないのと同じ。そこに星がまたたいていて、やっと空と呼べるものになります」
アツミさんが手を広げると衣装はパーッと一緒に広がって、ふわふわと揺れる。
まわりのみんなは風船を膨らまし始める。
「空には、たくさんの星のエネルギーが詰まっています。ほら」
膨らませた風船を手放すと、風船が、それぞれに勝手な方向に飛んでく、風船を手放した星たちはまた次の風船を膨らませる。
「それぞれの星にそれぞれの思いがあります。夜空を目を凝らして見てください。星は瞬いています。それは星からあふれた思いです」
あたしが最初に考えていたのとは、かなり違ったものになったけれど、でもそれで良かったと思う。あたしが考えたセリフのままでいいという人はそのまま、あたしのセリフを使ったけど、それでもかなり直したし、実際にそれを言う時には何かしらが変わって行った。その人自身の言葉になるのだ。
みんなで作り始めたら、どんどん違う考えも出てきて、周りの人たちの動きをどうするか、背景をどうするか、つぎつぎに意見が出てきてふくらんでいった。
風船を膨らませるというのは、アツミさんの考えだったし、音楽担当は皆の希望に合うように音楽を探し、考え、それがダメだと言われればまた探し、考えた。全員が参加して、セリフを言いたくなくても、ただ舞台に立って、ライトを点ける。それでりっぱなその人の役になるのだ。
あたしは、かなり満足して、宇宙を舞台にするのは、すごくいい考えだったな、と自分でちょぴり自慢したい気分になっていた。
やっと自分たちの演劇が終わったことで、あたしはすごくホッとしていた。最後だと思うといろいろな思いが押し寄せてきていて、頭にその思いがいっぱいになっていて、言葉にするには難しい感じだった。
三日目。最後の劇が終わった後、校長先生のお話があり、十二年生とのお別れのあいさつが終わった。会場からどどっと人が帰って行って、会場にはどんどん人がいなくなる。片付けの生徒がお掃除を始めて、あたしもそれを手伝った。
トモミもイスなどを片付けていて、ときどき目が合うと、笑いあった。アツミさんも片付けていたけれど、アツミさんはまた以前の固い表情になっていて、誰とも目を合わせないでもくもくと片付けていた。
アツミさんは、帰りがけにあたしの所にやってくると、
「成功だったね! ありがとう。あたし、なんだか頭が痛いから、もう帰るね」
と例のとろけるような笑顔で言った。頭が痛いのに…。あたしはそのアツミさんの後姿をしばし見つめてしまった。
アツミさんは出口近くにいたトモミにも声をかけて、トモミも何か言って、そして会場を出て行った。
あたしはなんだか一人で帰りたくない気分だった。そのあたしの気分が通じたかのように、トモミがまたいつものように走り寄ってきた。でも、何か少しおかしい。トモミはなんだか少しさびしそうに笑うと
「ね、今日、どこかに寄って帰ろう!」
と言った。
「うん。あたしもそんな気分だったの。寄って帰ろう!」
あたしも心の底からそう思っていた。
「ねえ、少し静かな場所がいいな。ヒトミに話しておきたいことがあるから」
トモミがやけに真面目に言う。
「話って…。いつも話して帰っているじゃない。毎日のように!」
「そうだけど…。座って、ヒトミの目を見て、まっすぐ話したい」
「げ! なに、それ。重たい話ってこと?」
「そういうわけじゃないけど。アツミさんのこと、話したい」
あたしはちょっとムッとした。昨日だって一緒に帰ったのだから、昨日言っておいてくれたのなら良かったのに。
「パーラーに行きたいな」
「うんいいよ」
あたしも、まだ引っ越しすること、ママと一緒に暮らすことをトモミに話していなかったじゃないか。それを話すちょうどいい機会かもしれないと思った。
あたしは、トモミをスクーターの後ろに乗せて、少し遠くのミキムラのフルーツパーラーに行くことにした。本当は二人乗りは得意じゃないけど、しょうがない。念のためにいつも予備のヘルメットをサドルの下にしまってある。
ミキムラのフルーツパーラーには、ママと一緒に行ったことがある。でもお友達と一緒に行くのは初めてのことだった。
お店の前に小さい花壇があって、その花壇の見える席があたしのお気に入りだ。
そのお気に入りの席が空いていたので、二人で喜んだ。
「ミキムラ、あたしも大好きだよ! いつもママと来るの!」
とトモミが言った。
メニューを見て、すごく二人で悩む。絵本みたいに、色鉛筆描きのパフェがたくさんならんでいる。そのページを見ているだけで楽しい。
「あたしは、やっぱりイチゴだな」
とトモミが先に決めた。
「うーん。悩むけど…、あたしもイチゴかな」
ふたりで同じイチゴパフェをたのんで、むかい合うと、なんだかすごく変な感じがした。トモミと仲良くなってからこの二年、いつも教室の隣の席か、スクーターを押しながら並んで帰る時におしゃべりしていたけれど、こんな風にかしこまって向かい合って座ったことがなかったのだ。
「ねえねえ、話って何?」
「すごいこと」
トモミが目を輝かせる。
「あのね。アツミさんが、先週、うちに遊びに来たの」
あたしは、たぶん、目をパチクリした。
「ね。ごめん。ヒトミ。なんでヒトミのことお家に誘わなかったのかって、ヒトミ、そう思うよね。まず、そのことから話さなくちゃあならない。だから、ちゃんと座ってお話したかったの」
あたしは、たぶん、まばたきもできなかった。いったい、なんと返事したらいいのか、見当もつかなかったのだ。
「ね、あたしのママのこと話したことあるよね」
「う、うん…、なんのことだっけ?」
「ママってね、すごく身体が弱いってこと」
「そういえば…、そうだったかな?」
「ママはね、とにかくあたしのことをすごく心配してくれるの。あたしのこと、宝物って言ってくれる。そしてね、あまり心配しすぎると、寝込んじゃうの。それはね、時としてすごくわざとらしいな、と感じることもある。あたしが、だんだん大人になってきて、そういうことがね、見えるようになってきたの」
「うん」
「ママはね、桜東通学校に通うことには、反対だったんだよ」
そこで、二つのパフェが運ばれてきて、ウェイトレスさんがいなくなるまで、話はちょっとお休みになった。
二人の間にパフェが並ぶと、顔が少し隠れるし、パフェに少し気持ちが動くから、話が聞きやすくなったように感じた。
「もともとママはあたしのこと、外に出したくなかったの。どうしてお家でサテライト校を受けないのかって、毎日のように泣いて、泣いて、トモミはママよりも学校のお友達と仲良くなって、それで幸せなの? なんて言うんだよ。まいっちゃうよ。それに、どうせ通学校に通うのなら、もっとお金持ちの人が集まっている良い学校、セキュリティーがしっかりしている通学校にしなさい、って言ったの」
あたしは、だんだん返事をするのが面倒くさくなって、イチゴを突っつきながら、目で相槌を打って、聞いていた。
「あたしは、ママとはうまくやって行きたいって思ってる。ママを怒らせたくないし、泣かせたくもない。ママとお買い物に行くのは楽しいし、お話するのも楽しい。ママがいつも気持ち良く、あたしのことかわいがってくれる時が好き。
でもさ、どうしても桜東通学校に行きたかったの。だって、あたしが知っている昔の学校の様子に一番似ているし…、ママやママのお友達のおばさま方のことも好きだけれど、ママやおばさまたちが、好きなものは、あたしが本当に好きなものとは違う。あたしは本を読んだり勉強したりすることが好きで、桜東通学校ではそれがすごくシンプルな形でできそうな気がしていたの。それに皆で演劇をするのもおもしろそうだった。
キヤ シンヤってうちの通学校の出身だよね? 俳優ではダントツうまいって思わない? そういうところではけっこう評価されてるもん。うちの学校。
でもママにはそんなこと言ったってわからないだろうし、あたしが説明してわかってもらう気もなかった。だから、ママの言うとおりの通学校に通おうかなとも思っていたの。」
「… …」
「でもね、でもね、パパが言ってくれたの『学校くらい、トモミの好きな所に通わせてあげよう』って。『自分の行きたくない学校にいやいや通うなんて、させたくない』って。それってすごかった。いつもパパはママを大事にしていて、ほとんど何も言わないから、それがすごくカッコよくて、重たくて、ママもはは~って、何も言わなくなった。あたしはうれしかったよ」
「…、…」
いったいトモミはこんなに遠くの方から話をして、何が言いたいっていうんだろう。あたしにはまだ見当もつかなかった。
「でもね。あたしが桜東通学校に通うことが決まってからは、ママは寝込むことが多くなった。お家に帰ってもね、具合が悪いって言って寝ているの。お食事とかはちゃんと家政婦さんが来て作ってくれていたし、あたしは、ママに顔を見せて、ママのお話を聞いて、お家にいる時はママが喜ぶようにしていたの。
一年経った頃くらいから、ママも慣れてきて、あたしの通学校のお話を聞きたがったり、あたしのお友達に会いたいと言うようになってきたの。そのころから、ママは学校のお友達を連れていらっしゃって言ってくれるようになったの。あたしもお友達にお家に来てほしいとずっと思っていた。いつも。一番、ヒトミに来て欲しいと思っていた。いつも」
声に出さなかったけれど、「あ!」と心の中で思った。いつもトモミが言いたそうで言わない言葉。「ねえ、ヒトミこんどさ…」。で、あたしが聞き返すと「なんでもない」って言う。あの言葉に続くのは「お家に遊びに来て」っていうことだったのだ!
「でも、あたしにはわかっているの。ママはヒトミのことが気に入らない」
びっくりした。こんなこと、真正面から言われるなんて。
「ママは、いつも言っている。ヒトミが住んでいる地区の人とは付き合ってはいけませんって。桜通学校にはそういう所からも子供が通ってきているから、だから反対したのだって。そういうお友だちには気をつけなさいって。
もちろん、あたしはちゃんと説明して、ママにわかってもらおうとも思った。でもわかるんだよ。ママの心の中にはすごい厚い壁みたいなものがあって、それは今のあたしの力ではどうやっても動かせないものなの。それを動かそうとすると、ママも具合が悪くなるし、あたしもすごく暗い気持ちになる。
その点、アツミさんだったら、大丈夫。アツミさんの住んでいる所は問題ないし…。それにアツミさんはステキだから、お話ししてみたいと思っていたから、思い切ってあたしが誘ったら、すぐに来てくれたの。
ヒトミのおかげだよ。あの劇の練習が始まってから、あたし、すごくアツミさんと話しやすくなったの。セリフをどういう風に言ったらいいかとかね、お話しするきっかけがたくさんできたの。でね、アツミさんって一度話してみるとね、とっても暖かくて、良くて、楽しい人なんだよ! ヒトミのこともほめていたよ。あのシナリオがあったから、どんどん話が進んで、みんなでまとまって良かったって」
あたしは何でもないような顔をして、パフェをもう半分食べていた。今までに感じたことのないようなヘンテコな気分だった。
「怒った?」
あたしがずっと黙っているからか、トモミが気にして、聞いてきた。
「怒ってない」
「じゃあ、何か言って。今までのところまでの話、どう思う?」
「どうって…」
あたしはパフェをかき回す。
「トモミのママが言っているのはおじいちゃんのことだよね。たぶん、おじいちゃんが『外された』人だからだよね。」
「そこまで…、わからない」
「そうだよ。でも、おじいちゃんは犯罪者じゃないよ。ただ、おじいちゃんが正しいと思ったことを通そうとしただけなんだよ。それがおじいちゃんの勤めていた会社の偉くて裕福で、代々そうやって偉くて裕福に暮らしている人のことを脅かしたの。おじいちゃんは会社を辞めさせられたし、いい仕事にも就けなくなってお、お金もなくなった。
でも、おじいちゃんは、今だってその考えを間違えているとは思っていないよ。ただ、今の世の中には通用しない。長いこと押さえつけられて、エネルギーもなくなった。だから、静かに暮らしているんだよ。おじいちゃんがどんなにやさしくて、ステキで、あたしのこと思って、毎日真面目にしっかり働いているのか、あたしは毎日見ているから、よく知っている」
おじいちゃんのやさしい笑顔が浮かんで、あたしの目から涙がこぼれた。
「ごめん。ヒトミ」
「いいの。これは説明とかしてわかることじゃないから…」
「それで、こう言いたいの。あたしは、ママのお家でママの世話になっているうちはヒトミをお家に誘うことはできない。ママによけいな心配かけたくないし。桜東通学校自体のこと、だめな所だと思って欲しくないし、いろいろ言って欲しくないから」
「そんなこと、どうでもいいよ」
「よくない。まだ続きがあるの」
トモミって、なんでこんなにまで正直に、あたしが嫌な気になることまで全部あたしに話してしまうんだろう。あたしは、つい溜息ついてしまって、ぼんやりとトモミを見つめた。
「あたしは、ずっとヒトミとお友だちでいたい。こんな風に、ヒトミを邪魔にしたみたいにしてアツミさんを誘ってしまったけど、そのことについては、気を悪くしたとしてもしょうがないと思ってる。あたしはいつか、ママの手を離れて、あたしの考えだけで生活できるようになったら、いつか、ヒトミ、あたしの家に来て!」
「バカみたい!」
と言って、あたしは笑った。
「いつも、あたしのこと『ぐるぐるの考え』になってるって、トモミはからかうけど、今日はトモミがぐるぐるの考えになっているよ。それに、まだ、そんな先のことまでわからないよ! その時になっていないんだから、今から約束しても意味がないよ」
「でも言って! ずっとお友達でいてくれるって!」
あたしはすっかりシラケ切ってしまって、今流した涙が嘘のように引っこんだ。あきれた顔を隠すように、グラスの底に残っているアイスを長いスプーンでかきあつめた。
「あたしも、トモミに言わなければならないことがあった!」
今度はあたしが話す番だった。
あたしは、ママと東京で暮らす決心をして、もう四月には桜東通学校から転校することをトモミに言った。
「ウソ!」
トモミは、悲しそうに言った。
「ホントだよ。いつだって」
「あたしが、アツミさんと仲良くなったからって、それだからって、意地になっているんじゃないよね?」
「バカじゃないの? それを知ったのは今日でしょ! 違うに決まっているじゃない」
「じゃあ、遠く離れても、友達でいよう!」
「トモミ。わからないよ。友だちでいようなんて…それは、自然に続いたり、続かなかったりすることで、約束したりすることじゃないと思う」
きっぱり言うとトモミの顔がなんだかごっつくなったので、すかさず付け加えた。
「でも、あたしは…、トモミと友達でいたいって思っているよ」
「ありがと!」
ごっつい顔がほころんだ。
「今のところはね!」
そんな先の約束まで自信が持てないから、ついそう言った。こういう時には、どうでもいいって気持ちになってしまう。
「ヒトミって、なんか冷めてる」
「トモミって、なんか暑苦しい」
いつもだったら、ここで二人で大笑いしていたのかな? でも今はそういう気にはなれなくて、ちょっとニッコリして、あたしはトモミをトモミのお家の近くまでスクーターで送って行った。
スクーターから降りたトモミが、急に泣き出した。しゃくり上げるように泣いて、泣いて、止まりそうもなかった。「バイバイ」も言えなくて、ちょっと手を上げると、泣きながら家に向かって行った。
「この、スクーターの名前はラビットだよ!」
トモミの背中に向かって、あたしが言った。ほかに言う言葉を思いつかなかった。
「うん。わかってる」
トモミは振り返って涙を拭うと、悲しそうに笑って、お家の方に走って行ってしまった。
それから、八年生の最後の日まではたった三日しかなかった。
最後の日に、あたしとトモミはとうとうアツミさんに水色のケーキをプレゼントした。
「一緒に食べませんか?」
とあたしが声をかけて、ホールで三人で座った。
ケイエスのケーキの箱の中には、三つの水色クリームのケーキが入っていた。
「ああ、これ。ブルーベリーよね」
アツミさんが言った。
なんだ、やっぱり知っていたのか、知らないのはあたしだけだったのか。
「ここのケーキはどれもおいしいよね」
アツミさんが喜んでくれたので、あたしはうれしかった。
「残念ね、ヒトミさんが学校を辞めてしまうなんて」
「ええ。でも、来年の通学校祭には見に来たいなと思っているから、みんなにがんばってもらいたいな」
「そうね」
「ねえねえ、なんでヒトミがアツミさんにそのケーキプレゼントしたいか、知ってる?」
トモミが話に入り込んできた。
「アツミさんがいつも水色のお洋服を着ているから、水色のクリームのケーキだって! お洋服の色と食べ物なんて、関係ないのに」
フフフとトモミが笑うと、アツミさんがちょっと不服そうな顔をした。
「水色か…」
あたしとトモミがちょっと目くばせする。
「これは、空色って言ってもらいたいな」
アツミさんは自分の着ているシャツを引っ張った。
「水の色って、もっと強い色よね」
「強い?」
あたしとトモミが同時に声を上げる。
「そう。太陽の下で光っている海って、グリーンだったり、マリンブルーっていうみたいにもっと濃い色だったり、『ここにいます!』っていう、強い感じがする。
あたしのイメージする色は空色で、もっと薄くて、何もないかなって感じの色」
「そう?」
「そうよ。この世から消えてなくなってしまいたいな、って思った時に、あ、空になればいいんだ、って思ったの」
「へえ~」
言いながらも、アツミさんのセリフを思い出した。
『空だけでは何もないのと同じ。そこに星がまたたいていて、やっと空と呼べるものになります』
「それに、空には触れない! 水には触れるけど」
あたしとトモミはうんうんとうなずき合った。
ホールを出ると、「じゃあね」と手を振って、アツミさんが先に帰って行った。
あたしとトモミはいつものようにスクーターを引っ張りながら、並んで歩いた。
「落ち着いたら、遊びに来て」
あたしが言った。
珍しく、トモミは何も返事せず、下を向いてしまった。
「大丈夫だよ。今度はおじいちゃんの家じゃないから、遊びに来ても」
そういえば、あたしにはお家にお友達を呼ぶ、なんて発想はなかったんだな。今までは。
「いつかさ、家にも遊びに来て」
トモミが言って、別れた。
もう桜東通学校には来ないんだ。ここに来ないあたしって、どんな生活になるのだろう。あたしはスクーターに乗って、いろいろ新しい生活を想像していた。
四月。新しい生活が始まった。
ママのマンションは高いビルの二十一階だった。家の外は車も人も多くて、「さすが都会」とあたしは思った。
おじいちゃんの暗い湿ったお家に暮らしていた毎日は、どんどん遠のいていった。
あたしは、九年生になり、中央公園通学校に通うことになった。ここもとてもシンプルな通学校だった。家から歩いて通える。中央公園の中にあって、図書館とカフェ、公園事務所が一緒になっている三階建てのビルの三階に教室がある。木々に埋もれているから、森の中の学校みたいに感じる。ちっとも都会って感じがしない。あたしは見学に来て、一度で気に入ってしまった。
九年生は十人。そのうち八人が女子でみんなとはすぐに仲良くなれた。まだ一緒に帰ったり、お家に行ったりというようなお友達はいないけれど、みんなサッパリしていて、自分の世界を持っているっていう感じで、これから、いろいろわかってくることがあるのかな…。とっても楽しみだ。
ママは遅くなることが多いので、家で一人で過ごすことが多いけれど、勉強したり、本を読んだり、時々おじいちゃんやトモミに電話してみたり、好きな映画やアニメを見たり、絵を描いたり、パソコンをやったり、やることはたくさんある。
おしゃれな雑貨屋さんやスイーツの店、お洋服のショップなどがあって、街を歩くのも楽しかった。
それに…、ママが忙しいので、あたしが料理をすることにした。パソコンでいろいろな料理のレシピを探して、近くのスーパーに材料を買いに行く。おじいちゃんが作ってくれた煮物の味を思い出して、おじいちゃんに作り方を聞いたり、モロッコとかポルトガル風なんていう料理を自分なりにアレンジしてみたりして、まだこちらに来てやっとひと月だけれど、毎日すごく「充実してる」という感じがしていた。
五月の連休にはおじいちゃんの家に行ったり、その間にトモミと会ったり、おじいちゃんの畑を手伝うことにしていて、それも楽しみだった。
「ね、ヒトミに会ってもらいたい人がいるの」
連休になる二日前の朝、あたしがお弁当を詰めていると、仕事に出かける前に、ママが急にあたしの後ろからあたしの両肩を両手で軽くつかんで、そう言った。
あたしが振り返ろうとすると、
「こっちを見ないで聞いて」
と言うのだ。あたしは返事できなくて、目をパチクリした。
「あのね。その人はヒトミのパパなの」
あたしはますます返事ができなくなって、こんどは瞬きもできない感じになって、顔が強ばった。
「ヒトミがおじいちゃんの家にお泊りに行く前にね、会ってほしいの。だから…、もう明日しかないから、明日の夜にね、どこかでお食事しよう。心づもりしておいてね。じゃあね、行ってきます」
ママはそれだけ言うと、先にさっさと仕事に出かけてしまった。
あたしは身体も頭の中までも固まったしまったみたいになって、次に何をしていいかわからなくなった。
「そうだ! お弁当、お弁当」
と自分に言い聞かせるように言うと、中身を詰めたお弁当箱をハンカチでくるんで、リュックに入れた。そうしたら、猛烈に腹が立って来た。
なんだって、ママは急に、こんな朝に、大事なことをいとも簡単に言うのだろう。あたしの目も見ずに! すごく複雑な気持ちがぐるぐる渦巻いてきて、涙が流れてきた。ママって勝手すぎる!
そのまま、今手に持っているものを全部ぶん投げて、テーブルも何もひっくり返してしまいたいような気持になった。でも、もう学校に行く時間だった。あたしは顔を洗い直し、深呼吸して、自分の顔を見つめた。
目が赤い。
「ママのバカ! バカ! 大バカ!」
鏡の中のあたしに訴え、タオルをぐるぐると振り回した。それでも腹が立って、バシバシとタオルで流しを鞭打った。深呼吸した。さらにもう一度気持ちを落ち着けて、学校に向かった。
いろいろ、わからないことが頭の中でぐるぐる渦巻いていた。なんだって、今なの? パパの話なんて、一度も聞いたことがないのに! どうしてママはいつも急にそういうこと言うの? いったいどこのだれなのだろう。パパって。
ありがたいことに、学校に行ってしまったら、少しは気持ちが紛れた。ママはそれを計算して、朝のバタバタしている時にあたしに言ったに違いない。一緒に暮らすようになったら、ゆっくり話ができるなんて、うそっぱちだったじゃないか!
結局、ママはいつも忙しくて、あたしが寝てから帰ってきたり、あたしが学校に行く頃には眠っていたり、今日みたいにあたしより早く出て行ってしまったり、こういうの「すれ違い」って言うんじゃなかったっけ? そうして、あたしに考える時間を与えずに、もう「明日」パパと会う約束をしていたんだ! あたしの時間なんか気にせずに。
また腹が立ってきた。
でも、まだトモミみたいな友達はいないから、それを誰かに話すわけにもいかない。
結局、あたしはどうすることもできずに、その日、ママの帰りを待った。
ママとは話せないまま夜になった。その日もママは遅くて、あたしは先に寝ることにした。でも頭の中がぐるぐるしていて、ちっとも眠くならない。
もう明け方になってから、ぐうっと眠った。アラームが起きる時間を告げても、身体が言うことをきかない。どうにかこうにか起き上がって、キッチンに行くと、ママのボイスメールがあって、今日、パパという人と会う時間と場所が入っていた。
ママに話しかけようと思ったけれど、ママはぐっすり眠っていた。しょうがない。覚悟を決めよう。お弁当は作ることができなかったっし、朝からヘトヘトっていう感じだった。やっとこ学校に行った。一日、気もそぞろだった。
一日通学校に通うことがこんなにも重労働みたいになるなんて! 通学校を出るころになっても、まだお腹の中にフツフツとママに対する怒りの塊が残っていた。
中央公園通学校のある公園を出たところに、深緑色のジープが止まっていた。そこが待ち合わせ場所。そのジープの窓からママが手を振った。まったく、いい気なものだ。あたしは知らん顔して通りすぎてやろうか、と思った。
あたしの顔はふくれ面だった。と、運転席に座っていた男の人が出てきて、あたしにあいさつした。ごっついジープだったからごっつい人が出てくるのかと思ったけど、細い、優しそうな目をした人が出てきて、男の人というよりは中性的な感じだった。
そして、「ヒトミ シンタロウと言います」と手を差し出した。
あたしは、心臓が止まるかと思った。「ヒトミって…」。
その人は、ニッコリ笑うと、「さあ、乗って、乗って」と助手席のドアを開けてくれた。
「ねえヒトミ、もしパパと暮らして、パパの名字をもらったら、ヒトミ ヒトミだったね」とママが笑いながら続けた。「今からでももらえるのよ。その名前が良かったらね」
街には不釣り合いなジープは走り出し、涼やかな風が入ってきた。
「今日はテントでできた個室のあるレストランに行こう。そういうのヒトミちゃんは好きかな?」
「おいしいものが出てくれば、なんだって好きよ。ね、ヒトミ?」
ママが勝手にあたしの気持ちを言う。また腹が立ってっきて返事をする気になれない。あたしの頭の中は真っ白だった。でも、このシンタロウって人の話を聞いてもいいかなと思い始めていた。その声はすんなりとあたしの心に届くような感じがした。
「おじいちゃんは、元気かな」
ポツリとあたしが言った。調子のいいママに釘を刺したい気持ちだったのだ。
「元気よ。それに、もうすぐ会えるでしょ」
あたしが黙っていると、ママはまた勝手に話し始めた。
「ヒトミはおじいちゃんのお家の方に住んでいた方が良かったの?」
「べつに…」
「ママはね、どうしてもあのお家を出たかったの。それは、おじいちゃんを否定するという意味じゃないの。あの場所にいるとね、レッテルを貼られてしまうの。それは、ママには耐えられないことだったの。でもね、レッテルははがれない。出たくて出たくてがむしゃらにいろいろなことやって、ママはやっとそれに気が付いたの。貼られても気にならないようになるしかないんだなって。それがやっとできるようになったのよ」
「そう?」
「ママはうれしい。ヒトミはそんなこと気にせず育ってくれて」
「そう?」
「そうだよ。ママもヒトミを見習わなくちゃ」
「ママ、あたしはただおじいちゃんが好きなだけだよ。それに、空になればいいんだよ。空にはレッテルが貼れないから」
あたしはぼんやりとアツミさんと話したことを思い出していた。
ジープの座席は少し高いから、行きかう車を見下ろしているみたいでおもしろかった。
「ね、ヒトミ、こちらのヒトミさんと来月、インドネシアに行くことになったの。お仕事がらみだけどね、ヒトミも行くでしょ?」
ママがまた勝手なことを言っている。
「一緒に行ってくれるとうれしいな」
シンタロウさんがこっそり言った。
返事はしたくなかった。あたしは明日のお弁当のことを考えていた。今朝、持っていけなかったから、その分をお弁当にして、おじいちゃんの分も作って持っていこう。冷蔵庫に残しておいたって、ママは食べやしないから、たくさん作って持っていこう。だって、自分で作れる小さいことしか想像できないし、どうせあたしの思った通りにはいかないのだもの。そのほかのことは、考えたってしょうがない。
今はただ、ジープの外の景色と、これから行くレストランのことを楽しみにしよう。
(おしまい)
水色のケーキ 2. [水色のケーキ]
「ほらこれ」
と、トモミが指差した。
ケイエスのレジの所には縦長のケーキのボックスがある。その中に丸いケーキが並んでいて、たしかに水色のクリームがたっぷりのっているのがあった。クリームの上に生のブルーベリーがポコポコと三個のっている。
「なーんだ」
「ねえ、買う?」
「買おうか」
「あたしは、ピンクのラズベリー味がいいな」
それで、トモミはピンク、あたしは水色のを買って、公園に移動した。二人でベンチに座った。座ると風をちょっぴり冷たく感じる。でもカッカしていたからかな、なんだか気持ちいい。
「ねえ、さっきの話の続きだけどさ」
と、あたしは話し始めた。
「アツミさんの誕生日に、あたしはこの色のクリームのケーキを贈ったらどうかな、ってずっと考えていたんだよ」
あたしはケーキを目の高さにかざして見た。なんだかすごくうれしくなってきていた。
「そうなんだ」
「だって、アツミさんていつも水色のもの着ているでしょ。だからね」
あたしは水色のケーキをぐるりと見て、どこからかじりつこうか迷っていた。
「ヒトミって、ほんと、考えがぐるぐるーってなるんだね。だって、あたしには洋服の色と食べ物の色は関係ないって思えるよ。アツミさんの洋服が水色だからって、食べる物も水色が好きなんて変だよ。色と味って関係ないもん。だいいち、水色の食べ物自体、珍しすぎる」
トモミは、唇についたピンクのクリームをなめながら、ふふふと笑った。
トモミに言われると、秘密を打ち明けたみたいな、妙な恥ずかしさがあって、それをごまかすように、あたしはケーキにかぶりついた。そしてあたしはトモミに言い訳した。
「それだったら、贈ったりしなくて正解だったね。それに…、なんだかいつも近寄りがたいから、ケーキを買ったとしてもけっきょく渡せなかったかもしれないよね。そんなケーキを持って行って、どんな風に言ったらいいかわからないもの…」
「ヒトミ、またぐるぐる~ってなってるよ。贈ったり買ったりしなかったのだから、もう考えてもしょうがないよ」
「じゃあ、トモミはどうなの? アツミさんの誕生日に何かしようと思っていたんでしょ?」
「ちがう」
「じゃあ、何で今日になって急に誕生日のこと言い出したの?」
「さっき、教室の出口でアツミさんとバッタリ一緒になって、それで『さよなら』ってあいさつしたの。そうしたら、急に誕生日のことを思い出したの…」
トモミは急に遠くを見つめるような目つきになって、言葉を濁した。そして
「どうする?」
と、あたしの方をまっすぐに見た。
「どうするって?」
「アツミさんに、そのケーキをプレゼントしてみる? ヒトミと一緒にだったら、渡せる気がする」
「やだ、今さら」
あたしは、恥ずかしくなってちょっと赤くなる。話が途切れるともっと恥ずかしさが目立ってくる。だからあたしは食べ続け、話し続ける。
「それにしても、こんなに簡単に見つかるとは思っていなかったよ…。水色のクリームのケーキ…。これ、おいしいね」
そうして、あたしは五歳のあたしとママと、水色のクリームのケーキを売る店と、オレンジ色の電気自動車が止まった交差点の思い出をトモミに話した。
「ヒトミって、なんでそんなに小さい時のことを覚えているの? あたしは何も覚えていないよ。今、気がついたらここにいるって感じ」
「でも、この間ママから電話があった時に聞いてみたらね、ママはちっとも思い出さなかったから、もしかしたら、ただの夢だったのかもしれないね」
「夢だとしたら、それを覚えているなんて、もっと驚異的!」
トモミは何にでもすぐに驚く。あたしの何でもないところにも。そんなところがとってもおもしろい。
「じゃあ、これでアツミさんの誕生日を祝ったことにしよう! アツミさんには言えなかったけれど、今、ここで二人で祝ったんだから、あたしが証人になるよ」
トモミがまたふふふと笑った。
さっきまでトモミのことに腹が立っていたけれど、そんな風に提案してくれるトモミのことが「輝く人」みたいに思えてきた。
「ね、ヒトミ、今度さ…」
トモミがこっちを見て、何か言おうとした。でもそのあとの言葉が出てこなくて、なんだかあいまいに笑って下を向いてしまった。
「ね、なになに?」
あたしが聞いても
「なんでもないんだよ」
とさびしそうに笑うだけ。そんなことがときどきある。いつもトモミはここで話をぷっつりとやめてしまう。
「いいねー」
あたしは指についたクリームをなめたあと、わざとらしく空を見上げてそう言うと、トモミもぐっとアゴを突き出して、空を見上げた。
「いいねー」
「いいねー」
それから、風が吹いたら、それがくすぐったいように感じて、二人でいつまでも笑っていた。寒さはどこかに行ってしまったみたいだった。
家に帰ると、家の中は真っ暗だった。
「ただいまー!」
じっとりと湿って、家の中の空気が重たくなっている。そこを突き破って通るように、あたしは声を張り上げた。
「おじいちゃーん! ただいまー!」
シーンとしている。おじいちゃんは畑かな。
桜東通学校がある桜市は東京からはEXで一時間。桜市の中心地に近くて、人もビルも多くて賑やかだ。おじいちゃんとあたしの家はそこからスクーターで三十分走った、ずっと田舎の方にある。おじいちゃんはずっと畑をやっている。だから真っ黒で細くて、しっかりしている。
「おーじーいーちゃーーん!」
あたしは玄関に靴を脱ぐと、もう一度大きい声で呼んでみた。
「おお。ヒトミか…」
おじいちゃんは十一月なのに、白のランニングにステテコみたいのをはいて、のっそりと奥の部屋から出てきた。
「ああ。ずいぶんと寝てしまった」
そしてにっこりと笑った。
「お帰り。ヒトミ」
「ねえねえ、夕飯は何? 今、何か食べるものある?」
ケーキを食べたけど、あたしのお腹はもうグーと音を立てていた。
「干しイモでも食べたらどうだ?」
そしてまたにっこりと笑った。
「おじいちゃん、今日はどんな一日だった?」
毎日学校から帰ってくるたびに、あたしは一応、おじいちゃんにそう聞いてみる。おじいちゃんは、必ず首を傾げて、考えるふりをする。
けっきょくおじいちゃんはにっこり笑って。「同じだ」と答える。そして「ヒトミは?」と聞いてくれる。ここまでは、おじいちゃんとあたしの帰りのあいさつセットになっている。
それからは、あたしが朝学校に行くときに気がついたことやら、学校での一時間目、二時間目、ランチ、三時間目、四時間目、五時間目のことを詳しく話す。今日は、そのあと、トモミがあたしに追いついてきて、アツミさんとのことを話したことまでを話した。
「そうかー」
おじいちゃんは、ただニコニコしているだけだ。本当にわかっているのか、わかっていないのか、わからない。とにかくあたしは一日のことを話したということで、ホッとする。
「干しイモ、焼いて食べるかい?」
おじいちゃんが言った。
「うん。焼いて食べる」
あたしが繰り返した。
あたしはおじいちゃんの後ろについて歩いて、「ねえねえ、トモミのことどう思う?」と聞いてみる。「スクーターのエンジンかけてるのに引っ張るなんて、危ないよねえ」
おじいちゃんは、ただニコニコ笑って、干しいイモをレンジに入れている。
「ねえ、おじいちゃんは、どう思うの? 危ないと思わないの?」
あまり質問攻めにすると、おじいちゃんは困った顔をする。
「まず、おまえがヒトミだろ。友達がトモミ、今話に出てきた人がアツミ。おじいちゃんには、その違いがわかるまでで精一杯。なんだってみんな同じような名前なんだい?」
おじいちゃんがボソボソと言った。
あたしは、なんだか、おかしくなってきて、大声で笑ってしまった。そして小さいことに変にこだわる自分のことがちょっぴり恥ずかしいような気がした。
だからあたしは照れ隠しにまたいろいろおしゃべりをした。おじいちゃんは暗いキッチンで鍋を火にかけて、夕飯の支度を始めた。
あたしはおじいちゃんのこと手伝いながら、ケーキのことやら、今までにあったことやら、これからやりたいことやら、いろいろ、いろいろおしゃべりする。
おじいちゃんは、ただ聞いている。そして、
「そうだ!」
珍しく、おじいちゃんがあたしの話を止めて、急に言った。
あたしはびっくりして、たぶん、目がまんまるになっている。
「今日は、ママが帰って来るよ。遅くなるけれど、起きていてくれたらうれしいな、と言っていたよ」
「そう…」
ママはジャーナリストで、世界を飛び回っている。いつも時間が足りなくて、あたしと話している時間なんかない。少ない時間の中で、必要なことだけ質問してきて、必要なことだけしか話さない。
なんだか胸がドキドキしてくる。ママと会うのは久しぶりだからうれしい。
あたしはそのドキドキを隠すように、続けてまた学校の話を始める。そして夕飯の時までには、あたしは話し疲れてしまって、だんだんおしゃべりしなくなる。
そうすると、なーんにも音がない。おじいちゃんがテレビを点けた。
お腹もいっぱいになって、たいくつなテレビを見ていると、だんだんまぶたが重たくなってくる。もう眠たくて眠たくて限界に近くなる。もう寝ようかなと思う頃にママが帰ってきた。
「ごめん、ごめん、ヒトミ。五分でも十分でも早く帰ってこようと思ってがんばったんだけど、こんな時間になっちゃって」
あたしはたくさん話したいことがあったけれど、もう頭の中が眠ってしまいそうだった。
「ね、ヒトミ、大切な話があるの」
ママがやけに真面目な顔をして言い始めた。
「ね、来月くらいから、ママと暮らそう」
あたしはびっくりて、おじいちゃん方を見た。いっぺんに目が覚めた。
「暮らすって? このお家じゃあない所で暮らすの?」
「そうよ。おじいちゃんを一人残して、ヒトミはママが住んでいるマンションに来るの」
「え? じゃあ学校は?」
「学校なんてどうにでもなるじゃない。サテライト校を選べばいいし、もし通学校に通いたいなら、ママのマンションからでも通える学校はあるわよ」
「桜東通学校は?」
「それは…、通うのはちょっと無理かな」
ママと暮らしたいとは思っていた。でもそれだからって、おじいちゃんと別れるというのは…。それに、あたしは桜東通学校に十二年通うと決めていたのに。
「おじいちゃんは、どうなるの?」
「ここで暮らすさ」
おじいちゃんが、静かに笑って言った。
「おじいちゃんは一緒に住めないの?」
「それはね、ママもそうして欲しいから、おじいちゃんにも一緒にママのマンションに来て欲しいってお願いしたの。ママはそのつもりで広いマンションに引っ越しをして、用意していたのよ。忙しすぎて、なかなか計画が先に進まなかったけれどね。でもね、おじいちゃんはずっとこのお家に住みなれているし、畑をするのが好きだから、ここを離れたくないんですって」
あたしがおじいちゃんの方を見ると、おじいちゃんがニコニコ笑って、小さく何度もうなずいていた。
「ここに、ママも一緒に住めないの?」
あたしの声は涙声になってきていた。
「それは無理。こうやって会いに来るだけだって、やっとだもの。東京の方でね、決まった仕事が取れたの。だからね、今までみたいに、海外ばかりに行くことはないと思う。そりゃあときどきは行くけれどね。サテライト校にすれば、ヒトミも一緒に行けるようになるし…。通学校に通うにしたって、お休みすることはできるのだから、ママと一緒に外国に行くこともできるわよ」
まったく、考えたこともないこと、考えたこともない世界があたしの目の前に広がった。あたしもママと一緒に外国に行けるなんて、なんてすごいことだろう。
自分の顔がほころぶのがわかった。でも、はっとしておじいちゃんを見た。
「ヒトミはヒトミの好きなようにしなさい。じいちゃんはここで暮らすのが一番。気楽だしこのままがいい。ヒトミはヒトミでどうするのが一番か考えなさい」
おじいちゃんが、力強く笑った。
あたしは言葉に詰まってしまって、急に胸が締め付けられるように苦しくなって、何も言えなくなった。涙が今にもあふれてきそうだった。でも、こんなところで泣くなんていやだ。だから何も言えなくなった。
「ヒトミ、すぐに答えなくていいのよ。少し、よく考えておいてね。ママの仕事は一月から始まることになっているの。それからでも遅くないのよ。ヒトミは三月で八年生を卒業するから、それからでもいいのよ。ただ…、来月すぐにでも決心がつくなら、そうしてもらいたいな」
あたしは下を向いてしまった。
「すぐには決められない…」
それだけを言うのがやっとだった。あたしの頭の中には大きいぐるぐるの渦巻きができていた。今日は眠れないかもしれない。
「わかった。とにかく、考えておいてね」
それから、シャワーを浴びてベッドに入ってからも、いろいろいろいろ思いは渦巻いた。おじいちゃんは一人で寂しくないのだろうか。でも、おじいちゃんのためにここに残るなんてことができるだろうか。
朝、ママはもう出かけてしまっていて、ママのボイスメッセージが残されていた。
『ヒトミへ
毎日元気でやっているみたいですね。おじいちゃんから聞きましたよ。毎日毎日、学校のことをとても楽しそうに話ししてくれるって、おじいちゃんがうれしそうでした。
そんな調子で、元気でいてくれると、ママはとってもうれしいです。
仕事、仕事ばかりで、ヒトミとあまりお話しできないけれど、いつもいつもヒトミのことを思っています。
引っ越しの話、急なことになってごめんね。もっとたくさん時間を取って話してきたらよかったのにね。ずっと計画していたことなのだけれど、ちゃんと説明する時間が取れませんでした。ママの勝手を言って悪いと思っています。でも、もしヒトミが一緒に住んでくれたら、今までよりずっと多く話もできるし、いろいろ楽しいことがあると思っています。ママの所に来てくれたらうれしいな。とにかくヒトミの人生なのだから、よく考えてみてね』
今年度の学校祭の出し物について、話し合いがあった。学校祭は学年の変わり目の三月の終わりにある。十二年生の卒業式も兼ねている。これからは話し合いを重ねて、何をやるのかが決まったら、少しずつみんなで用意していく。
あたしたちのクラスは二十人ちょうど。全員出演者にはなれないけれど、裏方の仕事をするのが好きな人もいる。あたしは、どちらでもいい。裏方も楽しかったし、両方かけもちの年もあって、それはそれで忙しくて楽しい時間だった。
前の日にママと住む話が急に持ち上がって、あたしの心はふわふわ落ち着かない感じになっていた。
「三月の学校祭の出し物について、意見のある人は言って下さい」
ショウジ先生がぐるりと皆を見まわした。
あたしは一年かけて、次の学校祭の演劇について考えていたことがあった。でもどうしよう。手を挙げようか。でも、ママと今すぐ暮らすという思いがどんどん大きくなってきていて…、そうすると今度の学校祭には出られないことになる。どちらを選ぶかなんて、とてもできそうもないような気がした。ああ、ママと一緒に暮らして、そしてこの通学校に通うことができたら一番いいのに。
迷っていると、アツミさんが手を挙げた。
「全員が舞台に出るお芝居というのはどうでしょうか」
びっくりした。それこそ、あたしがドンピシャ! 考えていたことだった。
「みんなが出たら、誰が裏方をやるんですか?」
サイジョウ ヒロが言った。
「全部舞台の上に持ち込むの。デッキも、音響のものも。舞台の上で、ずっと二十人が一緒に舞台に立っていて、演じるのはどうでしょうか」
あたしのドキドキが激しくなってきて、心臓が胸を突き破って出てきそうに痛くなってきた。
「いいと思います!」
まず声を上げたのはトモミだった。あたしは死にそうに痛くなった胸を押さえた。完全に出遅れてしまったのだ。すごく悔しくて、爆発しそうになった。
「あたしも、いいと思います!」
悔しかったけれど、トモミの次に手を挙げて、あたしも大きな声で言った。
トモミが笑いかけてくる。だけどあたしは泣きそうな顔になっていた。たぶん。
「オレ、やだな。なんか、そういう、みんなで、みんなで、っていうのって、気持ち悪いと思います!」
ムナカミ タカシが手も挙げないで、席に座ったまま吐き捨てるように言った。
「じゃあ、タカシ君は、どういうのがやりたいの?」
アツミさんがすっと立ち上がって、タカシに言った。
「そもそも、オレ、パス」
タカシが言った。
「それもしょうがないわ。この学校行事は強制じゃないんですから」
ショウジ先生がなんか、女言葉で言った。
アツミさんが手を挙げて、またすっくと立ち上がった。
「しょうがないけれど、出るでしょ? 一緒にやるでしょ? タカシ君?」
その時のアツミさんの笑顔ったら、とろけるような、笑顔で、誰も無視できないな、という笑顔だった。いつもあまり笑っていないから、すごい武器だなと思った。タカシはたじろぎながら、小さい声で言った。
「え、悪いけど、パスさして」
「どんな役でもいいのよ。みんなでやりたい役を作るの。だから、タカシ君がただ立っているだけがいいなら、それでもいいし、タンバリンとかたたくとか、なんでもいいの。そこにいてくれるだけで」
まるで、あたしとアツミさんがシンクロしてるんじゃないかと思った。たぶん、あたしもそういうふうに言っただろう、そのままの答えだった。
「ま、その日、オレ、来るかどうかもわかんねーし、来るんだったら、ただ出るんだったら、いいけど」
「ほかには誰が何をやりたいですか?」
自然、アツミさんが全体を引っ張って進めるような形になった。
あたしの心臓はずっと痛かった。今手を挙げたら、飛び出すかも。でも、そこをがんばって手を挙げた。
「実は、あたし、だいたいシナリオを考えました。もちろん、それを使わなくても、それぞれがやりたいことをやるという形でいいのですが、全体を通して簡単な筋があって、それぞれにセリフがあって、それを詩を読むみたいにして、一人ずつ言っていく形がいいと思います」
「ああ、よびかけみたいなのかな」
とショウジ先生が言った。なんだか馬鹿にされたような気がして、自分の顔が真っ赤になるのがわかった。
「うん。卒業式らしくていいのではないですか?」
ショウジ先生がアツミさんを見た。
「そうですね…。何もないところから、みんなで作っていくというのがいいかなと思ったのだけれど、ヒトミさんが考えているシナリオがあるのだったら、それをもとにしてみんなで組み立てていくというのもいいかもしれません」
「いいと思います!」
トモミがまた言った。
帰り道、スクーターを引っ張って歩いていると、いつものようにトモミが追いついてきた。
「ねえねえ、びっくりだったね」
トモミは何か興奮しているみたいに、ハアハア言っていた。
「なにが?」
「なにがって、アツミさんに決まっているじゃない! アツミさんがあんなにいろいろ発言する人だなんて、思わなかったし、すごくカッコ良かったよね」
「そうかな…」
「ねえねえ、ヒトミがシナリオ書いているって、本当なの?」
「本当だよ」
「本当なんだ」
「そうだよ…」
「へえ」
なんだか、またトモミに対して、ふつふつと怒りの感情が心の下の方から沸き立ってきているのがわかった。
「今度見せてね」
「どうせ、今度の話合いの時には持ってくるもん」
「そうなんだ~! すごいねヒトミって」
「なにが?」
「いろいろ作るの好きだからさ、お話とか」
「そう?」
「そうだよ」
「ウソかと思った」
あたしはカチンときて、歩くのをやめた。
「いつ、あたしがウソを言ったの?」
「ううううん。ウソというのとは違うんだよね。たぶん、ヒトミにとっては空想なんだと思う」
トモミはいたずらっこみたいに、私の顔を下の方からのぞくように見た。
「なにが空想?」
「たとえばさ…、お母さんのこととか」
「え? ママのこと?」
「そう、ニュースキャスターで、世界を飛び回っているって。そんなお母さんだったらステキだよね、わかるよ」
あたしは、トモミにあきれてしまって、言葉が出てこなくなった。
「まあ、いいんだよ。なんでも。いろいろ、想像してふくらませた方が楽しいもん。そういうヒトミの話、あたし、好きだと思っているよ」
どういう顔をしていたらいいのか、あたしはわからなくなってきた。
「ねえねえ、また水色のケーキ、食べに行こうか」
トモミがうれしそうに言うのを見たら、なんだか心が氷みたいに冷たくなってきてしまった。
「今日は、やめておく」
あたしはそっぽを向いて、スクーターにまたがった。
「今日は、もう行くね」
つんとするのもいやだったから、あたしはトモミを振り返って言った。
トモミはちょっとふくれていて「うん、わかった」 と、ちょっとさみしそうに答えた。
「またね」
そのまま、さっと乗って行きたかったけれど、なんだか今度はトモミのことがかわいそうに思えてきて
「今まで言ったこと、ぜんぶウソじゃないよ!」
と言って、あたしはスクーターのモーターをかけた。
トモミがどう思っていようとどうでも良かった。あたしはもうすぐママと暮らすのだ。そうしたらトモミと毎日会うこともできなくなる。そう思うと、しんみりした気分になってきた。いつもつんつん怒っていたらつまらない。お別れするときには仲良しのまま、笑顔でお別れしたい。
ママの所に行くのは、やっぱり学校祭が終わってからにしよう。シナリオのこと発言してしまったから、途中で下りるのはいやだ。それこそ、ウソつきみたいになってしまう。
あたしの頭の中はぐるぐるにならずに、すごくすっきり、はっきりと答えを出すことができた。ママはきっとその答えを喜んでくれるはず。それに、そうやってきっぱりとここを離れるのも気持ちいいかもしれない、と思えてきた。
風はかなり冷たかったけれど、すごく気持ち良かった。今度の学校祭はあたしにとって特別な感じがする。あたしはすごく大げさな気持ちになっていて、目に映るものがすべて、きれいで尊いな、あたしは透明だな、なんて思っていた。
学校祭の劇がどんどん形になっていった。
舞台監督はすんなりとアツミさんに決まった。アツミさんは皆の前に立つと、いつもしゃきっとしていて、話を一つずつまとめていく。人を寄せ付けないような冷たい感じはまったくしなくなって、皆を包み込むような、暖かい広い心を持っている感じが伝わってくるのだ。
「ヒトミさんが考えてくれたシナリオを元にして、みんなで話を考えていきましょう」
なんて言うアツミさんは、まるで学校の先生みたいだった。
さて、あたしの作った話というのは…、まず舞台を暗くする。そして舞台の上は宇宙ってことにする。みんなはその宇宙の一つ一つの星になるのだ。そしてそれぞれの星のことを一人ずつが少しずつ話していく。
あたしのイメージでは一人ずつがペンライトを持っている。最初はそのペンライトを全員がつけて、ぐるぐると舞台を回る。そして、それぞれがそれぞれの場所に立ち、ある人は体育座りをして、ある人は椅子に座って、みんなが舞台にいる。それぞれのペンライトは舞台という宇宙のそれぞれの星になる。
「サリメタル星から来た、タールです」
今、オオワダ アツシが立ち上がって練習していた。
一人ずつが話している時には、話している人だけがペンライトを点けていて、ほかの人は消している。大きいライトが二つ、舞台の両端にあって、今はアツシにだけに当たっている。大きいライトの係りは決めていなくて、何人かが入れ替わって務める。
「みなさん、見えますか?」
アツシがライトを振って、話す。
「サリメタル星では、とうとう水が一滴もなくなってしまったのです!」
周りを取り囲んでいるみんながペンライトを点けてザワザワと揺れる。
「わたしたち、水の惑星、アクアシスから、水を運んでさしあげます」
水の惑星役のトモミが立ち上がって言った。
「おいおい」
シナリオにはないところで、ミョウジが立ち上がった。
「やっぱり、この話、無理があると思うな。わけわかんない星の名前がたくさん出てきすぎるよ。もっとわかりやすいほうがいいと思います」
「じゃあ、ミョウジ君、ちゃんと具体的に案を出して!」
とアツミさんがどなった。
「何をやるかとみんなで話し合って、みんなこれでいいということに決まって、それでこの話を進めているんですよ。忘れたんですか?」
アツミさんはいつもの怒り顔になった。
「そう言われても。ボク、具体的な案はないけど、このシナリオじゃない方がいい、ということだけが言いたいんです」
「今、ここで話すことじゃあないわよね。もう決まったことでこの話は進んでいるのよ。皆手を挙げて賛成してくれた。ミョウジ君は手を挙げられなかったのかもしれない。でも時間はあったのだから、個人的に話しに来てくれても良かったわよね。君は何も意見をいわなかったでしょ! そうやって後戻りしていたら、ちっとも先に話は進まないわ」
アツミさんは完全に怒っていた。
あたしが手を挙げて立ち上がった。
「じゃあ、ミョウジ君、どういうセリフが言いたいのか、言ってみて。それに合わせてミョウジ君のセリフだけを書き換えます。一つずつの星だから、そうやって変えることができるんです」
「え…。別に。オレ、音楽係やりたいです。それだったらセリフなくてもいいから」
「わかりました!」
あたしは、そう答えて座った。ミョウジにセリフがなくても、他の星が音楽の星のことを説明するセリフをつければいい。そんなことは簡単なことだった。
なんだか声が大きくなってしまったけれど、ちっとも怒っていなかった。みんながみんな、自分のパートをいやな気持ではなくてやってくれたら一番いい。本当に心の底からそう思っていた。
「どうですか? ミョウジ君、それでいいの?」
アツミさんはまだ少し怒っているような感じでミョウジに聞いた。
「はい。それでいいです」
「はい!」
ムナカミ タタヒロが手を挙げた。
「ぼくもセリフ言いたくないので、音楽係がいいです」
「ぼくも。サリメタルなんて言いたくないから、音楽にしたいです」
オオワダ アツシも手を挙げて答えた。おやおや、音楽係りが三人になってしまった。でもあたしは愉快だった。なんでだろう。たぶん、引っ越しのことがなかったら、猛烈に腹が立っていたと思う。引っ越してしまうのだ、と思うと、今この時間がすごく貴重に思えて、なんでも受け入れられる。不思議だ。すごく心の広い人になってしまったみたいで、気持ちよかった。
「ねえねえ!」
帰り道、またトモミがあたしを追いかけて来た。
「ヒトミ、大丈夫なの?」
「なにが?」
「男子が三人もセリフをいやがって。くやしくないの?」
「それが、ぜんぜんくやしくないんだよ」
「だって、どうするの?」
「そうだね。一人ずつがペンライト持っているでしょ。音楽係りのペンライトはどこかに固定して…。そうだ! 帽子とかに固定して、頭の上で点くようにするの! でね、キラ~って音が出るスズみたいのあるよね。タタヒロにはスズがいいよ。あいつ、ピアノなんか弾けないし。ミョウジはシンセサイザーできるから、それをまかせればいいでしょ。アツシもスズかな…」
いろいろ考えていると楽しくなってきて、あたしは一人でベラベラとしゃべってしまった。
「すごいね。ヒトミ…」
トモミがあたしの横顔を見つめていた。
「そお?」
「そうだよ。あんな勝手なこと言われたら、あたしだったら、待ち伏せして、たくさん文句言いたい」
「それもいいよね」
あたしはなんだかおかしくなって、笑い出してしまった。
「ね。じゃあ、あたしのセリフは増やしてね。あたしはたくさん言いたい!」
「いいよ!」
「楽しみ~」
トモミがそう言ってくれて、あたしはすごくうれしかった。それから、別れ道まで、あれこれ劇について話した。そうしたらどんどん新しいアイデアが生まれてきた。
すごく楽しかった。
家に帰ってからは、ミョウジ、タタヒロ、アツシの紹介のしかた、ペンライトの使い方を考えた。考えはスルスルすべり出るように出てきた。あたしは、なんだか天才になったような気がした。
まず、タタヒロが自分のペンライトを点けて、キラ~キラ~と音を出す。
「あれは、キラキラ星の音だわ」
水の惑星アクアシス…、つまりトモミが言う。
キンコンカンと、トライアングルをアツシがたたく。
「アングル星が答えている…」
全部、説明はトモミだ。
そうしたらすごくおかしくて、お腹の底から笑いがこみあげてきて、ひとしきり笑った。
「いいの? こんないいかげんで? え? え?」
あたしは声に出して自分自身に言ってみる。
「いいの、いいの」
自分の質問に声を出して答えてみる。バカみたい! おかしくなって、また一人でゲラゲラ笑ってしまう。そうやっている間に、またトモミのセリフを思いつく。それをそのまま声を出して言ってみる。
「ほら見て! 音楽の星たちが今、くるくると回り出した」
それでミョウジ、タタヒロ、アツシは三人でくるくるその場で回り出す。
セリフを言わないのだもの、ほかの星たちより動きが激しくてもいいだろう。
自分でもくるくると回ってみる。
「ひゃー、目が回る」
あたしは、しりもちをついて、おかしくておかしくて、またひとしきり笑った。
「どうした? ヒトミ。楽しそうだね」
部屋の外からおじいちゃんが声をかけてくる。
「うん。すごく楽しいことがあったの」
あたしはたまらずに、おじいちゃんにさっそく今作ったシナリオのくだりを説明した。
学校祭当日まで、本当に本当に毎日が楽しかった。
アツミさんがどんどんまとめてくれて、劇はどんどんまとまっていった。
ママから電話があった時、あたしはウキウキしていて、
「ね、ママ、見に来てくれるでしょ? 最後の晴れ舞台だもの。来てくれるよね」
珍しく、あたしはママに言ってみた。
小さいころからずっと、あたしはいつもママに遠慮していて、何か欲しいとか、してくれとかなんて、言ったことがない。初めてあたしはあたしがして欲しいと思うことをママに伝えたのだ。
「うーん」
ママは困ったような声を出した。
「ごめん。ヒトミ…。すごく行きたいの。でも行けないの。わかって」
心のどこかでは、わかっていたのだ。ママが来てくれないってことは。
「うん。わかってる」
そう言いながらも、とても複雑な気持ちになった。
「シナリオは読んだのよ。すばらしかった! ママ、すごく自慢に思っている。ぜったいにうまくいくに決まっている。学校祭の様子は学校から映像が配信されるから、それで見ることができるわ。もちろん、別媒体でちゃんと保存するよ! それを見るのがすごく楽しみよ」
いい答えだよね。ママ。ママはいつもそうやってあたしのこと応援してくれているのだ。でも、何か吹っ切れないような気持ちがモヤモヤとあった。
通話を終えてから、また頭の中にぐるぐるの考えが渦巻いた。
結局、あたしはママに従うしかない。ママがお仕事しやすいように、ママが住んでいるマンションにあたしが引っ越しするのだ。ママがあたしのために引っ越ししてくれることはない。
しょうがない。ママは「ヒトミの人生」って言っていたけれど、まだあたしの人生は始まっていないのだ。ママにくっついているあたしの人生なのだ。だって、あたしは一人では生きていけないんだもの。しょうがないよ。
ママと一緒に暮らすことがすごく楽しみだったのに、桜東通学校のみんなと一緒にいることの方が数倍楽しいんじゃないかと思えてきて、なんだかすごく悲しくなった。
(つづく)
水色のケーキ 1. [水色のケーキ]
この頃、通学校でアツミさんのことを見かけると、よく思い出すことがある。
それはたぶん、あたしが五歳くらいの時のことだ。
あたしはママが運転するオレンジ色のかわいいミニ電気自動車の助手席に座っている。そしてぼんやり外をながめている。
どこかの町の交差点で車が赤信号に引っかかる。
ちょうどあたしの目の高さにケーキ屋さんの小さいスクリーンがあって、そのお店で売っているケーキが一つずつ映像で紹介されている。イチゴのショートケーキ、モンブラン…といったおなじみのケーキや、名前はわからないけれどそのお店で作っている、かわいい、おいしそうなケーキがつぎつぎに現れては変わっていく。
あたしはわくわくしてきて、その映像にくぎ付けになる。
そうしたら見たこともないケーキが出てきて、あたしはびっくりして、自動車のウィンドウに顔をくっつける。
そのケーキの形は三角形で、それは丸い大きなケーキを切り分けたよく見かける形。でも、クリームの色が水色なのだ。いったいどんな味なのだろう。あたしは不思議に思って、もっとよく見ようとする。
と、ちょうど信号が青になって、車が走り出す。スクリーンの映像はもう次のケーキを映している。もう一度繰り返し見て、さっきの水色のケーキを確かめたいけど、車はあっという間にお店から離れて行く。あたしはお店のほうに首を回して、いつまでも後ろを向いて、そのお店がある場所を覚えようとする。
「どうしたのヒトミ、何かおもしろいものが見つかったのかな?」
ママがくすくす笑いながら聞く。
あたしはその、ママの笑顔を見ながら、言葉を飲み込む。そして「ううん、なんでもないの」と言った。
ほんとうは「今のお店の所にもどって!」と言いたいところだったけれど、そんなことは言えなかった。ママはいつも忙しいのだ。
で、そのケーキのことだけど、今、大きくなった自分の頭で想像するに、あれはソーダ味だったんじゃないかと思う。ソーダの色を薄くのばしたみたいな色だったのだもの…。
たったこれだけのぼんやりとした記憶なんだけど、学校でアツミさんのことを見るたびに水色のケーキが思い浮かんで、ママとどこかに行ったあの車の中のことを思い出すのだ。そして、あたしは小さかったんだなと思うだけで、胸がキュンとなる。
で、なんでアツミさんとケーキが結びつくかというと、アツミさんがいつも水色のステキなお洋服を着ているからなのだ。色からの連想で頭にぐるぐるといろいろな思いが渦巻いてしまうのだ。
アツミさんはワンピースを着ていることもあるし、ブラウスだったりスカートだったり、パンツだったり、生地は無地のこともあるし、花柄だったり、チェック、シマシマ、水玉のこともある。でもかならず水色が多い柄を着ているのだ。持ち物やなんかも水色のことが多い。色の濃さはまちまちで、薄い水色のTシャツに色の少し濃いめのジーンズだったり、いろいろな組み合わせで水色をステキに着ている。なんだかいいなと思って、いつも見とれてしまうのだ。
アツミさんの誕生日が近くなってからは、ますますあのケーキのことが気になっていた。あんなケーキを買ってプレゼントできたらおもしろいだろうなと思うからなのだ。
これだけ毎日水色のお洋服を着ているのだから、きっとアツミさんは水色が大好きなのだろうと思うのだ。
ちょっと待てよ。
あたしはあたしの考えを一応疑ってみる。好きでもないのに、水色を着ているということがあるだろうか?
たまたまアツミさんが行くショップでは水色のものしか売っていないとか? それとも、お母さんが水色のお洋服しか着てはいけません!って言うとか?
そんなことはない! ぜったいに、ない! アツミさんは水色が好き! だって、アツミさんはお母さんの言いなりに洋服を着るような人っていう感じがしない。
あのケーキを見つけることができれば、アツミさんとすんなりと話すきっかけがつかめるような気がしてくる。
アツミさんはこの春から、あたしの通う桜東通学校に転校して来た。
ずっとお家でサテライト校の授業を取っていて、初めて通学校に通うことにしたらしい。今はそういう人のことも転校生と言っている。昔は通学校しかなかったから、引っ越しなどで学校自体を移ってきた生徒のことを転校生と呼んでいたようだけれど。
ここ数年の間に学校は通っても通わなくてもいい場所になった。年々子どもの数は減ってきているし、外に子どもを出すことが危険だと考えている親が増えた。環境のこと、子どもに関心を持つ変な人のこと。いじめに遭うという心配。良い先生も減ってきているそうで、それだったら良い先生の良い授業だけを選んで受けた方がいいと思う人が増えた。団体の生活を望む間だけ通学校に通えばいいし、団体生活は水泳教室や、そのほかのスポーツサークルなどでもできるというわけだ。
今、子どもは家でもどこでも通信の授業を受けることができる。地域にある図書館や自治会館、ゲームセンターでも受けることができる。そんなサテライト校でも共通試験を受けて、単位さえ取っていれば卒業できる。そういう所には先生はいないけれど、担当の大人が見回わっている。場所によってかかる料金は違うけれど、行っている時間分の費用を納めればいい。好きなものから単位を取っていけばいいし、同じ科目の同じ内容でも、気に入った先生の授業を受けることができる。
義務教育の期間は十二年間になったけれど、十二年間分の共通試験をパスすればだれでも卒業できる。共通試験は、途中であきらめなければ、受かるまでテストを受けられる。十二年以下で早くパスすることもできるし、何年かかってもかまわない。十八歳になっていて、だいだい九年くらいまでの試験をパスしていれば就職はできる。卒業とは関係ない。
あたしは一年生の時からずっと通学校に通っている。通学校というのは、昔の学校みたいに毎日決まった時間に通う学校のこと。授業はサテライト校と同じようにスクリーンを通して受けることもあるけれど、先生の生の授業を受けることもあるし、朝と帰りに、ホームルームがあって、「起立!」とみんなで立ち上がって「おはようございます」と言ったり、「さようなら」と言ったりする。ちゃんとクラスがあって、自分の席がある。
あたしはそういう昔風の通学校に行ってみたいとずっと思っていたのだ。
桜東通学校は一五階建てのビルの七階と八階にあって、そのビルの一階にはコンビニとハンバーガーショップが入っている。他のフロアには会社とかクリニックとか、雑貨のショップなんかも入っている雑居ビルだ。近くにいくつかの通学校があるけれど、みんなそんな感じだ。
昔のような学校としての建物はどんどん減ってきている。昔の写真で見るような、大きい「学校」もあるにはあるけれど、だいたいは建物の一部が通学校として使われていて、ほかの部分は地域の施設になっていたり、住宅になっていたり、他の物として活用されていることが多い。
通学校自体を変わるのも自由だし、通学校に合わなくなったら、サテライト校を選ぶこともできるし、しばらくサテライト校を選んでいて、後から通学校に通い始める人もいる(アツミさんみたいな感じ。こういう人も転校生と呼ぶ)。同じ通学校に出たり入ったりしてもいいし、とにかくすごくいろいろな選択ができる。
桜東通学校のように十二年通して通える通学校は少ないらしいけれど、そこに十二年通して通う生徒も少ないみたいだ。
義務教育を終えてからは大学校に行く。これは昔からそうだったようだ。でも何々大学っていう大学の外枠はなくなった。義務教育を受けたという証明が必要なだけで、入学試験というものがなくなった。授業はほとんどサテライトで受けることができ、自分の必要や興味に応じて、好きな授業を選んで、自分でカスタマイズできる。実験や実習などがある場合は通学もする。
好きなように授業を選べるけれど、それぞれの講座に合格点を取るのは難しい。いくつかの試験と実習をパスしなければならない。卒業ってものがなくなったので、何の講座に何点取ってパスしているか、というのが就職の時の基準になる。
ただ漠然と講座を取ってもしょうがないから、カリキュラムっていうか…、何をどう極めたいかという自分の目的にしたがって学習計画とコースを設定するのが普通だ。
自分でコースを設定するのが面倒くさかったり苦手だったりする人のためには、いくつかのお勧めや、基本のコースも用意されている。雑誌や指南書もあるし、コース設定コンサルタントを商売にしている会社もある。市役所の専門コーナーに行けば相談に乗ってもくれる。
ネットを調べれば専門家が設定するコースがあったり、普通の人が自分の体験を通してコースの例を紹介していたり、簡単なイエス・ノー形式の質問をクリアしていけば、コースが選べるってのもある。
専門的な仕事に就くという目的があればコース設定はある程度決まってしまう。取らなければいけない講座がはっきり決まっているし、決められた講座に全部合格しなければ、国家試験を受けることができない。就職が決まってからも、何かしらの講座を受講している人がたくさんいる。
桜東通学校は七階に一年生から六年生までの六教室と図書館、談話室、保健室があり、八階には七年生から十二年生までの六教室と職員室とホールがある。
あたしは今、八年生だから八階の八番教室だけど、二十人しかいない。ほかの学年もそんなものだ。でも通学校を選んだ子だけが来ているのだから、だいたいは通学校が気に入っている子ばかりなのだ。中には家にいたくないから来るという子もいるけれど、それだって家よりは学校にいる方がいいから来ているのだから、好きってほどではないにしても、いやいや通っているわけじゃない。
あたしはおじいちゃんと二人暮らしみたいなものだったから(ママは忙しくてほとんど家にはいなかったのだ)、それに、近所には同じ年くらいの子どもがぜんぜんいなかったから、ずっと通学校に入るのを楽しみにしていた。そして、入学した時からずっと、とってもこの桜東通学校が気に入っている。
あたしの家はどの通学校からも遠かった。だからどこを選んでも通うのは同じだったと思う。でも、一年生のあたしにはどこがいいかなんかわからなかったから、ママが選ぶ所に通うしかなかった。今ならわかるけど、たぶん家は今よりもお金がなかったから、ここにしか入れなかったのだと思う。サテライトの端末は今も家には引いてないけれど、それを引くお金もなかったんじゃないかな、と思う。でも、一番シンプルな学校だったから良かったと思っている。
最近の通学校はいろいろな特色を売り物にしていることが多く、豪華ですごくお金がかかる所も多いのだ。革張りのソファとか、フェイクファーのソファがふかふかの絨毯の部屋に用意されている学校とか、飛行機の機内や、電車の社内風にできている学校もあって、そういう学校では先生もフライトアテンダントとか、車掌さんみたいな制服を着ているらしいし、いろいろな時代の教室を用意している通学校もあって、戦国時代のお城みたいになっていたり、中世のお城みたいな内装になっている学校も雑誌で見たことがある。ドレスとか着て授業を受けているのだ。その学校は、給食なんて、バカみたいに長い机で、給仕の人がいて、晩さん会みたいなのだ。まあ、毎日ではないようなことが書いてあったけれど、いろいろな趣味の人がいるものだなあ、とあたしはあきれてその記事を読んだ。
うちの学校は弁当制で、勝手に自分で食べたい物を持って来るのだけれど(もちろん買って来てもいい)、晩さん会というほどではないにしても、給食がすごく豪華で、ホテルのシェフのお料理を選べたり、各国の珍しい料理を選べたりする通学校もあると聞いている。勉強以外でいろいろ特色を出さないと生徒が集まらないと大人は考えているらしい。
桜東通学校の「売り」は…、一応演劇に力を入れているということ。年に一回通学校祭があって、その時には各学年一つの演劇を発表する。だから毎年、一つの演劇に関わって、十一の演劇を見ることになる。でもこの学校ではそれも強制はしない。関わりたくない人は出なくてもいい。
ちなみに、去年の十二年生の出し物は一人芝居だった。ほかの生徒はシラケてしまって、ミナカミさんという男子生徒が一人でがんばって作って、演じたという話だ。いろいろな人が「なぞの女性、ジョセフィーヌ」について語るというお話で、ミナカミさんは十二人もの人を演じ分けた。けっこうガッチリした体型の人なのに、なよなよとした女性も難なくこなして、まったく違和感を起こさせなかった。ジョセフィーヌの飼い猫も演じた。猫の着ぐるみを着ていたので、最初なみんなクスクスと笑ったけれど、そのうちしんとなって、猫だったら本当にそう言うだろうとみんな納得したと思う。すごいなと思ってどんどんお芝居に引き込まれた。昔の小説を下敷きにしてミナカミさんが脚色したということだったけれど、本当にお芝居が好きな人なんだなと思った。ミナカミさんは俳優のプロダクションにスカウトされたらしい。もう俳優の道を歩み始めているといううわさだ。楽しみだな。
今のところ、毎年どんな形であれ、各学年全部が参加しているけれど、きっとそのうちに誰も参加しない学年というのも出てくるのかもしれない。
あたしは特に演劇が好きというわけではなかったので、どうでも良かったのだけれど、これがけっこう楽しい。今年もあたしは通学校祭を楽しみに待っている。だから本当に桜東通学校に通っていて正解だったと思っている。
一年生から六年生まで、あたしは家に一番近い大きな駅までおじいちゃんと三十分くらい歩いて行って、スクールバスで通った。七年生からはスクーターの免許が取れるので、さっそく取って、今は大好きなスクーターで通っている。雨の日だってスクーターで通う。ヘルメットをして、完全防備で出かければ、雨の中を走るのも楽しい。もちろん晴れている日も楽しい。スクーターで風を切ると、心がすっきりしたような感じになる。ちょっとくらいいやなことがあっても、スクーターで走れば吹っ切ることができる。ああ、本当にこの通学校にして良かった、とつくづく思っている。そしてこのまま十二年生まで、あたしはこの桜通学校に通うつもりだった。
アツミさんが転校生としてやって来た日のことは鮮明に覚えている。ポカポカ暖かい、春の始まりという感じの日だった。空が珍しくきれいに澄み渡った日だった。
アツミさんの着ていたワンピースはやっぱり水色で、その水色を見たとたん、あたしは遠い記憶の中の水色のケーキのことを思い出した。そんなことずっと忘れていて、それまでちっとも思い出したことがなかったのに、ふっと頭の中によみがえってきたのだ。そしてその光景がすごくはっきりしていたので、自分でもびっくりしてしまった。
ショウジ先生が、教室にアツミさんを連れて来たのだけれど、ショウジ先生より、アツミさんの方が背が高かった。
ショウジ先生は男性に見えるけど、どちらかといえば中性的で、そんなに背が高い方ではない。でも、あたしのクラスの女子生徒ではショウジ先生より背の高い人はいなかったのだ。
「今日から、このクラスに通うことになる、アツミさんです。アツミさんは北上の方からやってきました。お母さんと暮らしています」
あ、それはあたしと一緒だわ、とあたしは思った。ただうちの場合、今、ママはほとんど都心のマンションで一人で暮らしていて、月に何度かしか帰って来ない。だから学校にはおじいちゃんと二人暮らしだと報告している。でも、あたしが小さい時は一緒に今のおじいちゃんのお家で生活していたし、おじいちゃんはママのパパで、おじいちゃんの家はママが育った家なのだ。
「じゃあ、アツミさん、自分で自分のことを紹介してくれるかな」
ショウジ先生が言うと、アツミさんは「はい」と言って、一歩前へ出た。
そのとき、なんだか教室全体が明るくなったような気がして、ドキドキした。明るい水色のワンピースだったから、そう思ったのかもしれない。首のところにピンクの花柄のスカーフをさりげなく巻いていて、真っ直ぐに伸びた黒い髪が肩でサヤサヤとゆれた。それもステキだなと思った。
「先生? 電子板に書いてもいいですか?」
とアツミさんがショウジ先生に言った。それは怒っているようなきっぱりとした言い方で、あたしは背筋をピンと伸ばしてしまった。
「ああ。好きなようにしてください」
ショウジ先生がふてくされたように言ったからかな、アツミさんはちらりとショウジ先生を見てから、電子板こんなふうに書いた。
『名前 アツミ アツミ
女性
誕生日 ××二五年一〇月三〇日』
クラスの中にどよめきが起こった。
私たちは八年生は、みんな××二八年生まれだった。
つまり、アツミさんは、ほんとうだったら、××二五年生まれの十一年生のクラスになっているはずだ。
「私は、一年から七年までは家でサテライト校を取っていました。それでそのあと…ここに通うまでの三年間は眠っていたのです。だから、三年も学年が遅れたの。おかしいでしょう?」
アツミさんは、おかしいでしょう、と言いながら、ちっともおかしそうな顔はしていなかった。
「なにか、アツミさんに聞いておきたいことがあるかな?」
先生は、ぐるりと教室を見回した。
「はい!」と手を挙げたのは、ショウジ先生の息子で、バラキ ミョウジだった。
ミョウジは言った。
「なんで、上の名前と下の名前が同じなんですか?」
どうして、そんなことを聞くのか、あたしにはわからなかった。だって「アツミ アツミ」って、ステキな名前だし、たまたま名字と名前が同じになる人だっていることはいる。ミョウジのこと、嫌な奴! と思って、頭に来た。
アツミさんは、そんなミョウジの質問にも真面目に答えた。
「さあ? 母と暮らしているのだけど、母の名字はミョウバンっていいます。でも、わたしは、アツミでいいと思っています。だから母と名字が違うことも、あたしの名前と名字が同じということも、ちっとも気にしたことがありません」
「じゃあ、お父さんの上の名前がそうなんですか?」
と、ミョウジが続けて聞いた。
「そうかもしれないですね。でも、あたしは、父のことはよく知らないんです」
それは珍しいことではない。あたしだって、お父さんのことは知らない。
でもあたしの名前はタカオカ ヒトミで、名字はお母さんともおじいちゃんとも同じだった。
「はい!」
ともう一人が手を挙げた。
「はい、モロオカ サユリさん」
とショウジ先生がサユリを指した。
「三年間寝ていたって…、何をしていたのですか? 病気だっのですか? それでもお家で学校は受けられたでしょう?」
アツミさんは、面倒くさそうにふっと息をした。
もう一度手を挙げていたミョウジが、先生に指されてもいないのに立ち上がって続けて言った。
「このクラスに入ることはないんじゃないですか? 十一年クラスに入ればいいのに! だって学年はどうにでもなるものでしょ?」
「そうかもしれません。でも、あたしは、三年間何もやっていなかったので、八年生のクラスから始めるのが正しいと思いました。だから八年生から始めることにしました。遅れたら、遅れた分は家でサテライト校を取って、共通試験を受けて、自分の生まれた年の学年に入る人が多いのかもしれないけれど、私はその分遅れてもいいと思いました」
アツミさんはさっきよりももっと怒った顔をしてきっぱりと言った。そうしたら、クラス内がしんと静まりかえってしまって、誰も質問する人がいなくなった。
そして、みんななんとなく、アツミさんのこと「近寄りがたい人だな」と思ったに違いない。クラスの中の空気を固くするような雰囲気が流れたからだ。
休み時間に、ホールに行くと、あたしと一番仲良しのナカムラ トモミが、あたしを目指して追いかけて来た。
「ねえねえ」
といつもトモミはおもしろがるように言う。
「なんかさ、アツミさんって気高いって感じだよね。なんで家にいないんだろう? 普通、ああいう感じの人ってサテライト校にすることが多いのにね。通学校に来ても楽しそうな感じがしないよね。わざわざ通学校に来ることないのにね」
「そうね…」
と、言いながら、あたしはなぜかムッとした。
「でも、アツミさんが通学校を選んだのだから、家よりは良い、ってことなのよ。だって、実際に学校に来てるんだから。それに学年を遅らせたことも、それがいいってことでしょ? あたしにはどうしてかはわかんないけど、それの方が悪いってことだったら来てないものね」
「まったく! ヒトミの言うことはいつも、ややこしいね!」
トモミが笑った。
「だって、通学校に来ても一人でいるのが好きな子はいっぱいいるじゃない! そういう子でも、家よりもゲームセンターや図書館よりも学校がいいから来ているんだよ」
「まあ、そうだけどね。でも、なんか気になる。普通、一人でいたい人のことって、気にならないのに」
それはあたしも同じだった。アツミさんのことがなにか気なった。
アツミさんは、学校を休むわけでもなく、授業があるときはちゃんと聞いている。通学校でも授業はけっきょくサテライト校とあまり変わりがないことが多い。スクリーンが大きいだけで、通信で受ける授業と同じようなものだ。でもときどきは先生の生授業もあるし、体育、理科の実験や家庭科の実習もある。アツミさんはすべての授業を休まずに受けていた。
でも、休み時間は一人で本ばかり読んでいる。それも、教室の自分の席で。アツミさんの席は一番奥の一番後ろで、学校に来てからは自分の席に座ったきり、あまり動かない。
みんなが気にしてチラチラ見ていても、関係ない。そばに寄って行って、話しかけてみたいけれど、人を寄せ付けない雰囲気を発していて、そばに近寄れない。
あたしだったら、一人で本を読む時は、ホールのベンチに行ったり、図書室に行ったりして、人がいない方が集中できるのだけどな。
と…、ものすごく前置きが長くなってしまったけれど、そんなわけで、あたしはアツミさんの誕生日をはっきりと覚えていたのだ。そしてそのアツミさんの誕生日の数日前から、ずっと「どうしよう」と考えていた。水色のクリームのケーキを見つけることができれば、それをきっかけに、アツミさんとお話しすることができるのじゃあないかと思ったのだ。けれど、そんなケーキは見つけられないまま、けっきょくアツミさんの誕生日はやって来てしまった。
なんにせよ、お誕生日ということで話すきっかけになるかもしれないから、あたしはカードでも贈ろうかと迷ったりもしたけれど、それもできなかった。急にそんなことしても、わざとらしいような気がした。アツミさんの誕生日はちゃんと覚えているんだよ、ってことは伝えたかったのに、それもどうでも良くなってしまった。
あーあ、どうでもいいや。あたしはそういうどうでもいい考えに捕まってしまう。そしてそのどうでもいい考えはぐるぐると頭の中を何重にも取り巻き、抜けられなくなってしまうのだ。
あたしはいつでも明るくて、楽しいことを考えるのも得意なのに、そういうつまらないことに捕まって何時間も過ごしてしまうこともある。そうすると、なかなか切れ目を見つけられなくなってしまう。
そういう、ぐるぐる巻きの考えに捕らわれているときは、ちょっと重たい気分になっている。だからとっても疲れてしまうのだ。
十一月になった。少し風の冷たい日もあるけれど、まだセーターなしで過ごせる。
アツミさんのお誕生日が過ぎてしまったからか、通学校でアツミさんを見かけても、なんだかシラけてしまう。アツミさんは相変わらず、周りの空気を寄せ付けないで読書に没頭していた。
月曜日の帰り、あたしがスクーター置き場にいると、いつものようにトモミが走り寄って来た。
「ねえ、ヒトミ! アツミさんのお誕生日、過ぎちゃったね」
トモミはいきなりそんな風に話しかけてきた。
「え? トモミも気にしてたの? アツミさんのお誕生日のこと」
「そりゃそうだよ。だって、あの人、はっきりと自分のお誕生日を電子板に書いたでしょ。その時衝撃が走ったでしょ。誰でも忘れられないよ。あれは」
「だったら、なんで今頃言うのよ!」
なぜだか知らないけれど、あたしはものすごく腹が立って、トモミを振り切って行きたい気になった。あたしはトモミに背を向けて、スクーターにまたがった。
「なんなの! ヒトミ! 何を怒ってるの?」
トモミはわけがわからなかったみたいで、あわてている。
「知らない」
あたしはプイと横を向いた。トモミの顔を見たくなかった。
「やだ。あたしを置いて、スクーターで帰る気?」
「知らない」
あたしはスクーターのエンジンをかけた。エンジンはドルドルドルと音を立て始めた。
「ねえねえ。アツミさんのお誕生日のこと言ったのがいけなかったの?」
エンジンの音に負けないように、トモミが大きな声で言っている。トモミはおもしろがっている。だからよけいに腹が立った。
「待ってよ、待ってよ!」
トモミがあたしの手をつかんだ。あたしの身体がトモミの方に傾いた。
「バカ! 危ないでしょ!」
スクーターがもう少しで走り出すところだったのに! 本当に危ない! もっと腹が立ってきたけれど、あたしはしかたなくエンジンを切って、トモミの横に並んだ。
あたしの顔は、どうしようもなく怒り顔になった。
「途中までスクーター、押して帰って! いつものように、一緒におしゃべりして帰ろう!」
トモミはあたしがムカムカしているのに、ぜんぜん気にしていないみたいに言った。だからもっともっと腹が立ってきた。でも、トモミは私の腕を放そうとはしない。あたしはムッとしながらも、トモミと並んで、スクーターを引きながら歩き始めた。
「その色、いつも好きだって思ってるよ」
と、トモミがあたしのスクーターに触った。
あたしは答えなかった。
もちろん、あたしのスクーターだもの、あたしだって好きな色だって思っている。それはオレンジ色で、ママが乗っていたミニ電気自動車みたいな色。ママと一緒にスクーターを選びに行った時、一番に目に飛び込んできて、一番に気に入って買ったのだ。
あの電気自動車がまだ家にあった頃は、ママはまだおじいちゃんとあたしと一緒に暮らしていて、忙しそうだったけれど、ときどきはあたしを車に乗せていろいろなところに連れて行ってくれたのだ。
「ね、何か言って!」
と、トモミがいたずらっ子みたいな顔で笑いながら、あたしの顔をのぞいてきた。あたしはもうどうしようもなくムカムカして、口をとんがらせた。
「このスクーターの名前、ラビットってことにしない?」
唐突にトモミが言う。いつだってそうだ。トモミはあたしの機嫌を直そうと思って、全く違う方に話を方向転換させようとしているのだ。あたしは黙ってスクーターを引っ張った。本当はトモミを引き離して、先に歩いて行きたかった。でも、スクーターが重たいからそうもできない。
あーあ、トモミのことなんか気にしないで、さっさとスクーターに乗ってしまったらよかったのに。とあたしは思った。
「ヒトミもアツミさんのお誕生日のこと、考えていたんだね」
トモミはぜんぜん平気で話しかけてくる。
「知らない」
「だったら、なんで怒っているのか教えて!」
トモミがあたしの手を引っ張る。
「痛いなあ。危ないでしょ。一緒に帰ってあげるから、もっと静かにして!」
あたしがキーキー声を上げると、トモミはちょっとしゅんとして、少し黙った。
そして、二人でただ黙って歩いた。
信号が赤になって、二人そろって止まった。
「ねえ、なんで今頃アツミさんの誕生日のことを言うの? 今頃言ったって、もうお誕生日が過ぎてしまったら、どうしようもできないでしょ!」
あたしは胸のムカムカを吐き出した。
そんなつまらないことで、あたしは泣きたくなってきていた。それで、あたしは言葉を切って、またそっぽを向いた。
「ごめんごめん」
トモミはまだおもしろがっていて、あたしの様子をうかがっている。
「ねえ。ヒトミ、教えて。お誕生日に何かしようって思っていたの?」
「知らない」
信号が青になった。二人でまたそろって歩き出した。
あたしはトモミを振り切ってしまいたいのに、トモミはまだしつこく着いてきて、あれこれ聞いてくる。
「ヒトミ、まだ何かしようと思っているのだったら、あたし、一緒にプレゼントとかしてもいいよ。気になっているんだったら、今からでもそうしようよ。お誕生日ってことじゃなくても、なんでもいいじゃない」
「バカみたい」
あたしは下を向いた。
「ねえねえ言ってみなよ」
トモミはまったくあたしの気分の悪いのなんて、どうでもいいんだ。あたしの気分をもっとかき回したいんだ。そう思ったら、また腹が立ってきて、あたしはトモミの目をぐっとにらんだ。
「こわーい」
とトモミが笑った。
「なんでそんなに怒っているのか教えて! アツミさんのことだからなの?」
「べつに…」
答えたくないのに答えてしまう。だからよけいにムシャクシャする。
「ね。だったら今からプレゼントとかしようよ。ねえ。そうしようよ、そうしようよ」
トモミが駄々っ子みたいに、言い出した。
「バカみたい…」
「バカでもなんでもいい。ヒトミが怒っている理由が知りたいだけ。ヒトミが怒っていたらずっとつまらないから、普通に戻ってもらいたいだけ」
トモミったら、なんでこんなに素直に真っ直ぐに話ができるのだろう。ちょっとくやしいけど、トモミがうらやましくなってきた。
「まあいいや。どうでも」
自然にそんな風に言えるようになってきた。
しばらくまた無言で歩いた。
あたしが力を込めて歩いているからか、トモミより少し先になって、トモミが少し遅れてあたしの視界から外れた。そうすると、またトモミが追いついてくる。スクーターが重たいからそれ以上引き離すことはできない。
トモミってしつこい。でも、あたしのこと気にしているからしつこいんだよね。どうでもいいと思ったら、もう違う方に行ってしまっているよね。
くやしいけど、あたしはトモミの方を少し振り向いて見た。
今度はトモミが少しふくれている。なのに、まだあたしの後ろを必死で歩いている。あたしはなんだかおかしくなってきた。
「ねえトモミ。水色のクリームのケーキがあったら、それ、何の味だと思う?」
あたしは遠回しに話を始めてみる。
トモミの顔がパッと輝いた。
「そんなの、ブルーベリーに決まっているよ!」
トモミは簡単に言った。水色のケーキのこと思い出してからずっと不思議に思っていたことなのに。
「そうなの?」
今度は急にトモミのことが偉い人のように思えてくる。
「そうだよ。そんなのどこでも売っているよ。見たことないの? オドロキー! ヒトミ、甘いもの好きなのに」
「どこで売っているの?」
「普通のコンビニだよ。その角のケイエスにもあるよ。ね、見てみようか」
トモミのほっぺたが光っている。そしてうれしそうに笑っている。
トモミに言われるままに、あたしはケイエスの前の駐輪場にスクーターを置くと、二人で一緒にケイエスに入った。
(つづく)






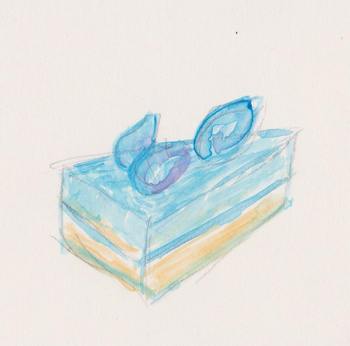

.jpg)

